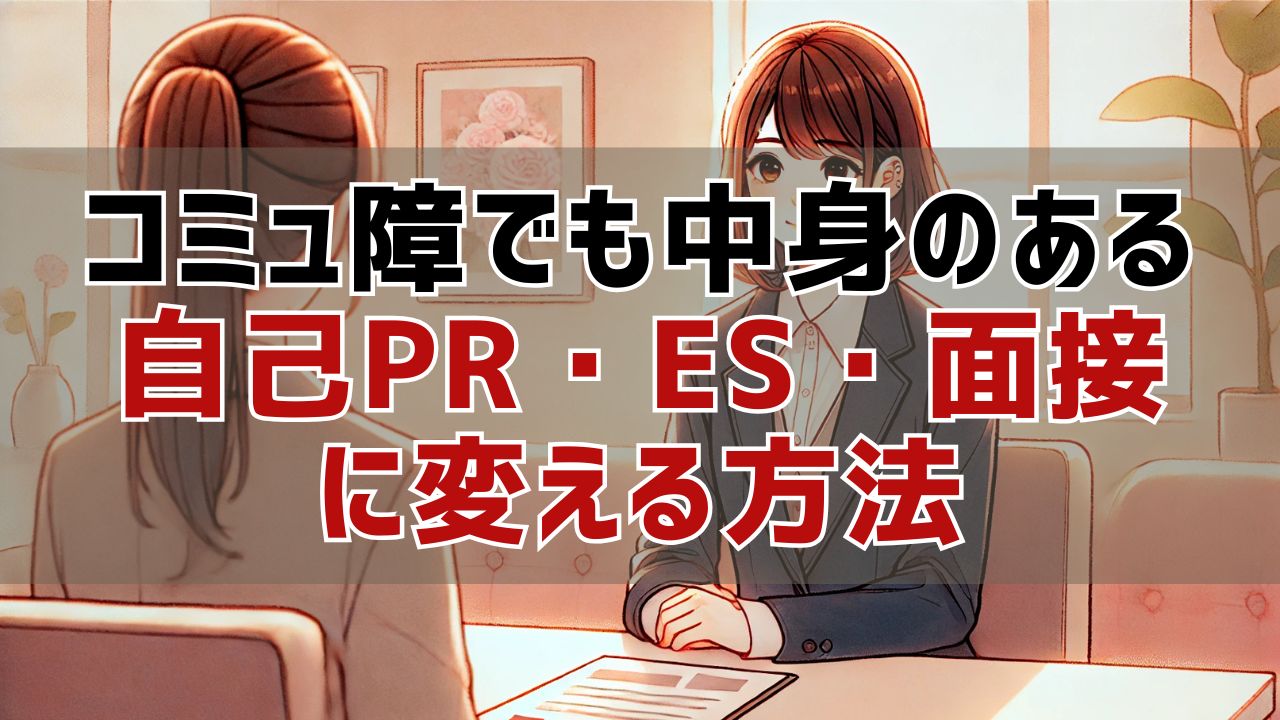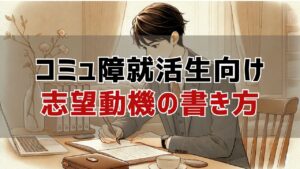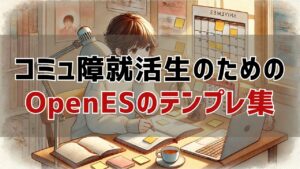「話が薄いって言われたらどうしよう…」
「面接でもESでも、いつも“なんか浅いな…”って自分で感じてしまう…」
就活でこうした悩みを抱えている人の中には、コミュ障気質によって“話を深める”ことが苦手な人が多くいます。
かつての自分もその一人でした。何を聞かれても表面的なことしか答えられず、「自分の話って中身がないな…」と落ち込むばかり。
でも、ある考え方と“話の整理の型”を知ってから、少しずつ変わり始めたんです。
この記事では、
- 話が浅くなる原因とコミュ障の関係
- 自己PRやESに深みを出すための構成の考え方
- 面接で“広がらない”を乗り越える具体策
- バイト経験など身近なエピソードを“中身のある話”にする方法
を、かつての悩みと元採用担当の視点の両方からお伝えします。
コミュ障の就活生の話が広がらない原因は何?
「話が広がらない」
「中身がないと言われる」
この悩み、就活中に本当に多くの人がぶつかります。
特にコミュ障気質の人は、“会話のキャッチボール”や“話を膨らませる”のが苦手だと感じがちです。
でもそれは、話す力が足りないのではなく、“深め方の視点”がないだけかもしれません。
会話が続かない・広がらないのは“話し方”のせい?
「私は話すのが下手だから…」
「頭の回転が遅いから、うまく伝えられない…」
かつての自分も、そうやって責めてばかりいました。
でも、採用担当として面接に立つようになって気づいたのは、
「話し方」より「話の中身の整理」ができているかどうかの方が大事だということ。
たとえ緊張して言葉が詰まっても、
- 話の流れがわかる
- 話の背景や考えが見える
- 誠実に伝えようとしている姿勢がある
それだけで「この人、いいな」と思ってもらえるチャンスはあります。
面接・自己PR・ESで「中身がない」と感じられる理由
コミュ障の人が「浅くなる」「中身がない」と言われやすい理由は、主に次の2つです。
- 理由①:行動の説明だけで終わっている
「〇〇をしました」だけでは、“なぜそうしたか”や“そこから何を得たか”が伝わらず、話が表面的に聞こえてしまう。 - 理由②:自分の思いや背景を省いてしまう
「どうせうまく話せないし…」という気持ちから、感情や気づきを言葉にすることを避けがち。
でも逆に言えば、この2点を補うだけで、話に深みが出て印象が大きく変わるんです。
「話を広げる」のは雑談力じゃありません。
- なぜそうしたのか
- どう感じたのか
- そこから何を考えたのか
これらの視点を入れれば、話はちゃんと“中身のある話”になります。
コミュ障でも中身のある話に変える就活エピソードの構成法
「そもそも大した経験がないから、話に深みが出ないんじゃ…」
そんなふうに思ってしまう気持ち、すごくよくわかります。
でも実は、エピソードの大きさや派手さは関係ありません。
ポイントは、“どう見せるか”。
つまり、語り方の構成次第で、どんな話も中身のある印象に変わるんです。
経験の大きさより「見せ方」が鍵になる
たとえば、「バイトで接客をがんばった」という話。
そのままだとごく普通に見えますが、
- なぜそのバイトを選んだのか
- 最初はどんなことが苦手だったのか
- どんな工夫をしたのか
- どんな変化や気づきがあったのか
こういった要素を加えていくと、一気に“その人らしさ”と“思考の深さ”が見えてきます。
採用担当の立場としても、同じような経験を語る学生が多い中で、「この人はちゃんと自分のことを振り返ってるな」と感じるのは、行動だけじゃなく背景や気持ちを語れる人なんです。
「大した経験がない」と感じる方には、ガクチカの掘り下げ方も参考になりますよ。
派手じゃない経験でも“語り方”で深みを出すコツをこちらで解説しています。
▼ ▼ ▼
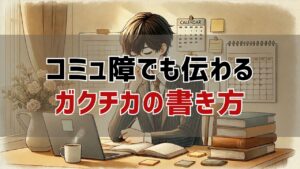
なぜ?どうして?を掘り下げれば、それだけで深みが出る
「何をしたか」よりも、「なぜそうしたのか」「どう感じたのか」の方が、面接ではずっと重要です。
これは自己PRでもESでも共通しています。
たとえば、「勉強を頑張りました」だけだと浅く聞こえますよね。
ですが、「グループ活動にうまくなじめず、自分が安心できる居場所を作りたくて勉強に集中するようになった」と語れば、人柄や背景が伝わる“厚みのある話”になります。
つまり、“掘り下げる力”さえあれば、どんなエピソードでも深く語れるということ。
これは、話し方のスキルではなく、“考える順番”を知ることで誰でも身につけられます。
自己PR・ESで使える「話を深める」3ステップ
「何をどう書けば深みが出るのか分からない…」
そんな人にこそ試してほしいのが、“話を深める3ステップ”です。
これは、私自身が面接で何度も失敗を重ねた末にたどり着いた整理法であり、採用担当としても「この流れで話されると内容がすっと入ってくる」と感じていた構成です。
ひとつずつ、具体的に見ていきましょう。
ステップ①:「なぜそうしたのか?」という動機を加える
まずは、「なぜその行動を選んだのか?」を言葉にしてみましょう。
私は大学1年のとき、あえて裏方のポジションにこだわって学園祭の運営に関わりました。
このままだと説明で終わってしまいます。
一方で、
私は大学1年のとき、あえて裏方のポジションにこだわって学園祭の運営に関わりました。
話すことが得意ではなく、表に出るよりも全体を支える方が安心できたからです。
と行動の理由を加えるだけで、自分らしさが一気ににじみます。
ステップ②:「何が難しかったか?」でリアルな厚みを出す
次に、その中で「どんな壁や難しさがあったか?」を加えてみます。
情報の行き違いで当日の動きがバラバラになり、焦ったことがありました。
ここで
自分が声をかけるのは怖かったが、伝達の仕組みを見直そうと提案しました。
など、不器用ながらも自分なりに動いた姿を見せると、印象に残りやすくなります。
ステップ③:「そこで何を学んだか?」まで書き切る
最後は、その経験を通じて何を得たのか、どう考えが変わったのかを伝えます。
話すのが苦手でも、自分の得意な方法で周りとつながれると感じ、自信につながりました。
この“気づき”の部分まで書けると、話は一気に「行動の報告」から「自分を知っている人の語り」に変わります。
この3ステップを意識するだけで、同じエピソードでも、「浅い」から「深い」へと印象が変わります。
面接でもESでも、「結局何を言いたいのか分からない」と言われてしまう人ほど、この流れで整理してみると、自分の中でも話がスッとつながるようになります。
面接で浅くならないための準備&答え方
「面接になると、話が広がらない…」
「自分の話って、途中で終わっちゃってる気がする…」
そんな悩みは、コミュ障就活生にとって本当に切実です。
でも、これは“会話が下手”だからではなく、“話の組み立てが準備不足”なだけであることがほとんど。
ここでは、話を深めるための準備方法と、当日の答え方のコツを紹介します。
回答は「結論→背景→気づき」の型で整理
面接で話が浅くなってしまう人の多くは、話の順番がバラバラだったり、途中で終わってしまったりします。
そこでおすすめなのが、以下の「話が広がる型」です。
- 結論(何をしたのか/強みは何か)
- 背景(なぜそうしたのか/どんな場面だったのか)
- 気づき(そこから何を学んだか/どう変化したか)
この順番で話すことで、相手にとってもわかりやすく、一歩踏み込んだ印象を与えることができます。
- 結論:私は“聞き手として支える力”を大切にしています。
- 背景:人前で話すのが苦手だったため、あえて裏方の役割を選び、相手の立場を想像するよう意識してきました。
- 気づき:その結果、周囲から“気が利くね”と言ってもらえるようになり、自分らしい関わり方に自信を持てました。
焦らず一言ずつ“情報を足していく”イメージで話す
コミュ障の人にありがちなのが、「一気に全部伝えなきゃ」と思ってしまって、かえって早口になったり、内容が飛んでしまったりすることです。
でも、面接官は一問一答で深掘りしていくもの。
最初からすべてを言い切る必要はありません。
むしろ、最初はシンプルにまとめておいて、「そのときはどう感じましたか?」と聞かれたら、少しずつ情報を足していけばOK。
面接は、“完璧に話す場”ではなく、“一緒に話を整理する場”。
そう考えるだけでも、プレッシャーがぐっと下がります。
話が浅く聞こえるのは、話し方ではなく“準備の仕方”と“構成の工夫”次第。
それさえ意識すれば、話すのが得意じゃなくても、ちゃんと伝わる面接になります。
さらに伝わる面接になるように次の記事もご覧ください。
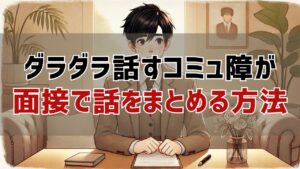
本番で「話がまとまらない」と焦ってしまう方は、こちらの記事の“話の型”を覚えておくと安心です。
【具体例】「バイト経験」を浅くない話に仕上げる方法
「バイトしか話せることがないんですけど、それって浅いですか?」
よくある相談ですが、バイト経験が浅くても薄くても関係がありません。
ここでは、よくある表面的な言い方を「中身のある話」に変える具体例を紹介します。
Before:「接客バイトをしていました」
たとえば、「接客バイトをしていました」の一言で終わってしまうと、内容がまったく伝わりません。
面接官としても「で、どういう工夫をしたの? 何を学んだの?」と聞きたくなります。
これは「行動」だけを切り取ってしまっているから、浅く感じるのです。
After:「人見知りで避けていた接客に挑戦した理由と変化」
同じ経験でも、こう言い換えるとどうでしょうか?
話すのが苦手だったため、大学では接客バイトを避けていました。
でも、“苦手なままでは社会に出たときに困るかもしれない”という思いから、あえて接客に挑戦しました。
最初はお客様の顔を見るだけで緊張していましたが、相手の反応を観察して、少しずつ自分なりの声かけを工夫できるようになりました。
結果として、“安心感がある”と指名されることもあり、話すことが得意じゃなくても、接し方で信頼を得られることに気づけました。
面接官からすると「苦手を放置しない姿勢」が見えて信頼できるという印象を持ってしまいます。
このように、
- なぜその行動をしたのか(動機)
- 何が難しかったか(リアルな壁)
- どう変化したか(気づきと成長)
という3点が含まれていると、話は一気に深くなります。
バイト経験は、型にはめれば立派な“中身のある話”になる素材です。
「すごい成果」がなくても、「自分なりに考えて動いた」という視点があるだけで、伝わる内容に変わります。
まとめ:話が浅いのではなく、“語り方の型”を知らないだけ
就活で求められているのは、完璧なスピーチでも、すごい成果でもありません。
本当に見られているのは、
- なぜその行動を選んだのか(動機・結論)
- 何にぶつかり、どう工夫したのか(過程・背景)
- そこから何を得たのか(気づき)
この3つがちゃんと自分の言葉で整理されているかどうか。
それだけで、エピソードの“深み”はつくれます。
「話が浅い」と悩んでいたあなたにこそ、この記事が、“語り方を整えるきっかけ”になっていれば嬉しいです。
「そもそも話の材料が薄い気がする…」と感じる方は、自己分析から見直すのもおすすめです。
強みを見つける方法はこちらで詳しく解説しています。