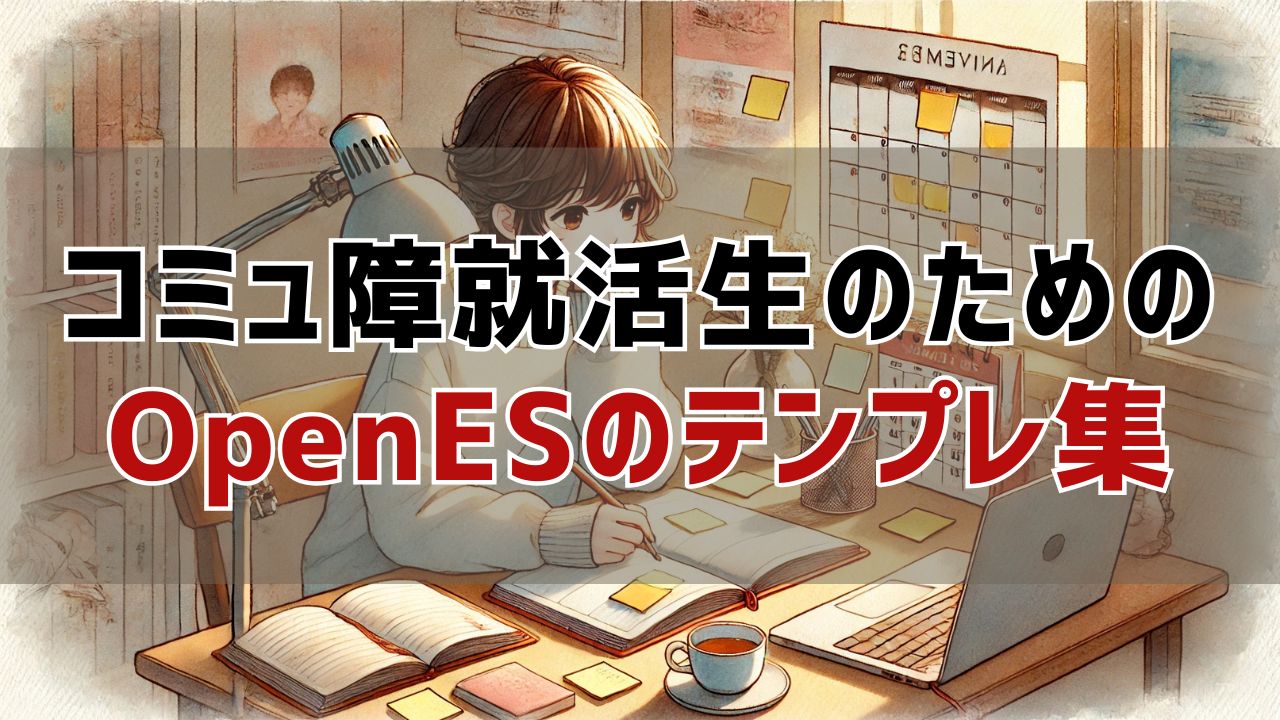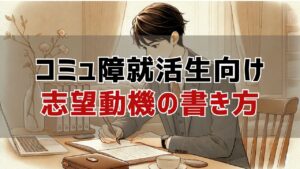「OpenESって何を書けばいいのかわからない…」
「何をどう伝えても薄っぺらく見えそう…」
そして、不安になって、結局テンプレっぽい文章を何度も書き直す日々。
そんなふうに悩んでいるコミュ障就活生は、実はすごく多いです。
でも、社会人になって採用担当としてOpenESを読む立場になった今、はっきり言えるのは
OpenESこそ、“話せない人”が自分らしさで勝負できるチャンスだということ。
この記事では、
- OpenESの特徴と、コミュ障就活生がつまずきやすいポイント
- 自己PR・ガクチカを“あなたらしく”仕上げる構成法と書き方
- 空白や模範回答を避けるためのNG&修正例
- 「話せない自分」を逆に強みに変える文章テクニック
を、かつて悩んだ就活生としての視点と、採用担当としての視点をまじえて紹介します。
「OpenESと通常のESの違いは何?」から始めるコミュ障向け対策
OpenES(オープンエントリーシート)は、リクナビなどのナビサイトを通して、複数の企業に同じESを送れる“共通エントリーシート”です。
つまり、一度書いておけばいろんな企業に提出できる便利な仕組みです。
なのですが、実はこの“共通”という仕様が、コミュ障就活生には意外と難関だったりします。
通常のESと何が違う?OpenESの特徴をざっくり理解
OpenESは、以下のような特徴があります。
- 自己PR・学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)など、記入欄が決まっている
- 文字数制限がある(大体400文字前後)
- 写真の添付や基本情報も一括で送るスタイル
企業ごとに質問が違う通常のESと違い、“誰にでも通じる文章で”“短く・簡潔に”書く必要があるのが特徴です。
この“簡潔にまとめる”というのが、話すのが苦手=説明でカバーするタイプの人にとって難しいんですよね。
私自身、最初のOpenESでは
「言いたいことが全然収まらない…」
「これじゃ薄すぎる…」
と、何度もやり直しました。
コミュ障が気をつけたい、OpenES特有の“地雷ポイント”
特にコミュ障の人が陥りがちな落とし穴がこちらです。
- 空白を避けるために“無難なテンプレ”で埋める
→ 中身が伝わらない - 文字数を気にしすぎて「結論だけ」で終わる
→ 人柄が見えない - 言いたいことが絞れず話がバラける
→ 印象に残らない
OpenESでは、「上手に話せる人」が有利というより、“自分の特性を整理して、端的に表現できる人”が印象に残るのです。
だからこそ、話すのが苦手なあなたでも、構成と書き方を工夫すれば、十分に勝負できます。
次のセクションでは、“話さない自分”だからこそ活かせる、OpenESでの書き方のコツを紹介します。
コミュ障の強みを活かす!OpenESならではの書き方のコツ
「OpenESって、話せる人向けでしょ?」
そう感じている人にこそ伝えたいのは、OpenESは“話せなくても伝えられるチャンス”でもあるということです。
ここでは、コミュ障就活生がOpenESで自分らしさを出すための、具体的な書き方のコツを紹介します。
書式が決まっているからこそ“話さない良さ”を活かせる
OpenESは自由記述ではなく、質問項目や文字数が決まっています。
これは、「自由にアピールして」と言われて困るコミュ障の人にとって、実は“安心できる型”でもあります。
つまり、
「何を書けばいいかわからない」ということは、「あらかじめ聞かれることは決まっている」ということ。
「どうまとめればいいかわからない」ということは「文字数制限があるので、長々と悩まなくていい」ということ。
このように捉えると、構成と焦点さえ決めれば、話せない人でも“整理された文章”で印象を残せるんです。
書ける欄が少ない=エピソードの取捨選択が大事
OpenESは文字数が少ないぶん、“全部盛り”ができません。
だからこそ大切なのが、「何を書くか」より「何を削るか」が大事になります。
自分が伝えたいエピソードの中で、
- なぜその行動をしたのか
- どう考えたか
- どんな変化があったか
この3つだけに絞って構成すると、“等身大の思考”が見える文章になります。
話すのが得意な人は、細かいニュアンスを声や表情で補えますが、文章だけで勝負するOpenESでは、考えの筋道が通っていることの方が重要です。
写真欄・簡易記述で「らしさ」を出す小ワザ
OpenESでは、写真を登録したり、志望企業によって簡単な記述を求められることがあります。
このとき、“完璧に見せよう”としすぎないのがポイントです。
たとえば、
- 表情が硬くてもOK。清潔感や服装に気をつければ問題なし
- 一言記述では、「話すのが得意ではない分、文章で丁寧に伝えたいと思っています」と書く
など、等身大のひとことが逆に印象に残ることも
“飾らない姿勢を出せるのは、実はコミュ障タイプの大きな強みです。
コミュ障のためのOpenES自己PRの構成ガイド
「自己PRって、話せる人じゃないと説得力出ないでしょ…」
そう思って筆が止まっているなら、大丈夫です。
OpenESの自己PRは、“地味な強み”こそ伝わる構成にできるんです。
ここでは、コミュ障の自分を否定せず、そのまま活かして伝えるための3ステップ構成を紹介します。
ステップ① 苦手の裏返しから“強みにつながるエピソード”を見つける
自己PRを書くとき、「まず強みを決めよう」と考えて手が止まってしまう人は多いです。
特に、話すことが苦手だと、「自信を持って言えるような強みなんてない」と感じてしまいがちです。
でも実は、無理に“強み”を言い切らなくても、自己PRの第一歩は踏み出せます。
最初にやってほしいのは、「自分が苦手だと思っていること」を、少し視点を変えて見直すこと。
そして、その“裏返しの特性”が表れていたエピソードがないか、思い出してみることです。
たとえば、こんなふうに裏返して考えると、自分らしい行動のヒントが見つかります。
| 苦手・不得意なこと | 裏返しの視点(特性) | 思い出すべき行動・場面のヒント |
|---|---|---|
| 話すのが苦手 | 相手の話をよく聞ける | 誰かのサポートに回った経験は? |
| 人前で話すのが怖い | 準備を丁寧に行う | 発表やプレゼン前に工夫したことは? |
| 自分から話しかけられない | 周囲を観察して動ける | 空気を読んで行動した経験、気配りした場面は? |
このように、「得意」とは言い切れなくても、“自分なりにこうしていた”という行動や場面を拾うことができれば、それが自己PRの材料になります。
私自身も、「堂々と自己主張するのは苦手だけど、準備と観察なら自分の持ち味として語れるかもしれない」と気づけたことで、エピソードが書けるようになりました。
このステップでは、“完璧な強み”をひねり出す必要はありません。
むしろ、「話すのが得意じゃないからこそ、こんなふうに動いていた」というような、等身大の行動エピソードを1つ見つけてみてください。
それが、自己PRの土台になります。
ステップ② 「なぜ?」の掘り下げで等身大の説得力を出す
次に、「その行動をなぜ取ったのか?」を掘り下げましょう。
たとえば、「大学のゼミ活動でのグループでの発表」というエピソードを1つ見つけ、深堀していくとします。
【1. 行動】
大学のゼミ活動で、4人グループでの発表を行う機会がありました。
私は話すことが得意ではなく、リーダーや発表担当ではなく、全体のスケジュール調整や資料の整合性チェックといった“裏方の役割”を自分から引き受けました。
【2. 背景の理由】
発表直前に、メンバー間でスライド内容に重なりがあることがわかり、慌てる場面がありました。
しかし、私は事前にそれを想定して確認用のチェックリストを作っていたため、それを使って整理・再調整を行い、無事に発表を迎えることができました。
人前で話すのが苦手なぶん、「どうすれば全体がスムーズに動くか」を事前に考えて準備することが、自分にできる貢献だと思って行動してきました。
【3. 得た視点】
このような役割を続ける中で、「全体がスムーズに進むには、表に立つ人だけでなく、裏で流れを支える人の存在が不可欠」だと実感しました。
話すのは得意でなくても、自分なりに周囲を見て動けることが、チームにとって必要な力になると気づきました。
このように、「行動」を「理由」と「気づき」で丁寧に掘り下げていきます。
「選んだ行動」だけでなく、「その背景にある理由や思考」が伝わると、“自分で自分を理解している人”という印象につながります。
元採用担当の私が見ても、こうした自覚的な文章は非常に読み応えがあります。
ステップ③ 入社後のイメージを“丁寧な表現”で補う
最後に、「この強みが仕事でどう活かせそうか?」という未来の姿を軽く添えておくと、印象がグッと深まります。
とはいえ、盛る必要はありません。
大切なのは“自分なりの言葉”で表現することです。
たとえば、
大きな声でまとめるよりも、気づいたことを静かに支える役割を大切にしていきたいです。
話すのは得意ではありませんが、周囲をよく見て必要なことを補う動きができると考えています。
こうした“静かな熱意”を感じさせる言葉選びが、OpenESではかえって響きます。
面接官も、「この人なら、話せなくてもちゃんと支えてくれそう」と自然に感じ取るはずです。
【コミュ障向け】OpenESガクチカの構成ガイド
「ガクチカって、サークルとかチーム経験がないと書けないのでは…」
そう思って手が止まっている人も多いと思います。
私自身も、就活初期は「リーダー経験もないし、語れることなんてない」と思い込んでいました。
でも、社会人になって採用担当としてESを読むようになってから気づいたんです。
「誰かと何かを成し遂げた話」よりも、「自分がどんな姿勢で向き合ったか」が伝わる話のほうが、印象に残る。
ここでは、コミュ障の人でも無理なく書けて、ちゃんと評価されるガクチカの構成法をお伝えします。
チーム活動じゃなくてもいい、一人で積み上げたことが武器
ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)というと、「チームで目標を達成した話」を想像しがちですが、OpenESにおいては“個人の努力”でもまったく問題ありません。
たとえば、
- 会話が苦手だから、発言しなくても評価されるような裏方の役割に専念した
- 対人関係に疲れて一人で過ごす時間が多かったが、その中で継続して勉強や資格に取り組んだ
といったことも武器です。
これらは、“周囲との距離感”に悩んできたからこそ生まれた選択であり、「どう向き合ってきたか」という視点を加えれば、立派なエピソードになります。
採用担当としても、正直な話「無理にリーダー像を演じてるな…」というESより、自分の立場でできることを誠実に取り組んだ姿勢の方が、ずっと好印象です。
ガクチカに「大した経験がない」と感じている方には、こちらの記事で“等身大で語れる例文とコツ”を紹介しています。
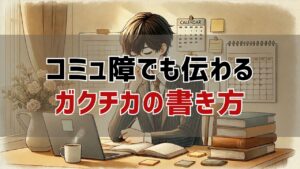
続けた理由、工夫したことが“思考力”として伝わる
たとえ小さなことでも、
- なぜそれを始めたのか
- 何が難しかったのか
- どうやって続けてこられたのか
こういった背景や工夫をきちんと添えることで、エピソードに“深み”が出ます。
たとえば、私が就活時代に書いたのはこんな内容でした。
私は大学時代、講義内容を毎回ノートにまとめ直すことを習慣にしていました。
人前で発言することは得意ではありませんでしたが、自分なりに理解しようと整理し続けることで、
ゼミ内で資料作成を任されるようになりました。
特別な経験じゃなくても、「どう考え、どんな工夫をしたか」が書かれていれば十分に評価される。
これは元採用担当としても、断言できます。
コミュ障がOpenESでやりがちなNG例と修正例
OpenESを書こうとするとき、
- 何を書けばいいかわからないから、とりあえず埋めてみる
- 文字数が足りないから、とにかくそれっぽい言葉を詰め込む
といったこと、ついやってしまいがちですよね。私もそうでした。
でも、採用担当として何百枚ものOpenESを読んできた立場から言うと、そういう“取り繕っただけの文章”はすぐに伝わってしまいます。
むしろ、“不器用でも自分の言葉で書かれているES”のほうが、ずっと印象に残ります。
ここでは、コミュ障の人がやりがちなNG例と、それをどう修正すれば“伝わる文章”になるかを紹介します。
NG例① 空白 or 模範解答まる写し → “あなたらしさ”が伝わらない
私はリーダーとしてチームをまとめました。責任感を持って目標達成に貢献しました。
正直、このような文面は内容の薄さ以前に、どこかで見たことある感が強くてスルーされがちです。
さらに、“自分で書いたのかどうか”が伝わらないと、「中身がない」と評価されてしまう可能性も。
私は人前で話すのが苦手だったため、グループ活動では主に資料整理や進行の補助に取り組みました。
自分から発言するのは難しくても、全体の流れを見て行動することでチームに貢献できると感じ、
後半は他メンバーから進行の確認を頼まれるようになりました。
自分の特性を隠さず、どう向き合ってきたかを素直に書くと、“らしさ”がにじんで伝わります。
NG例② 「頑張った」だけで終わる → 読む側の“納得感”が不足する
私はアルバイトで接客を頑張りました。常に笑顔で対応し、お客様に喜ばれました。
頑張ったのは伝わりますが、なぜそれを頑張ろうと思ったのか? どう工夫したのか?がないと、説得力が出ません。
人と話すのが得意ではなかった私にとって、接客は大きな挑戦でした。
最初はマニュアル通りの対応しかできませんでしたが、
お客様が困っている場面を先に察して声をかけるなど、自分なりの工夫を積み重ねました。
その結果、“ありがとう、助かった”と声をかけてもらえることが増え、少しずつ自信が持てました。
感情・背景・工夫の3つを加えることで、“納得感のある等身大のエピソード”に変わります。
「なんだか自分の話って浅い気がする…」と感じる方はこちらも必見です。
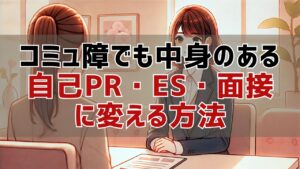
上記の記事では、“中身のある話”に変える考え方と構成法を解説しています。
OpenESで“コミュ障らしさ”を逆に武器にする書き方
「話すのが苦手って、やっぱりマイナスですよね…」
そう感じてしまうのも無理はありません。かつての自分も、「うまく話せない=評価されない」と思い込んでいました。
でも、採用担当としての経験を通じて見えてきたのは、“話せない人”には“話せる人”にはない魅力や強みがあるということ。
それを素直に伝えるだけで、むしろ好印象になることさえあるのです。
会話が苦手=観察力・継続力に置き換えるテクニック
話すのが得意じゃない人は、無意識にまわりをよく見ています。
声を張って会話をリードするのは苦手でも、
- 相手の表情の変化に気づく
- 一歩引いて全体の流れを把握する
- 空気を読みながら行動する
といったことが自然にできる人が多いんです。
また、人と比べることが少ないぶん、
- 同じ作業をコツコツ続ける
- 自分の中で工夫を積み重ねる
といった“継続力”や“誠実さ”も強みになります。
これらは、企業が求める「協調性」や「主体性」の一つのかたちです。
話せるかどうかではなく、“どう考えて行動してきたか”を見ている企業にとっては、十分にアピールになる要素です。
「話すのが得意ではないからこそ〜」の一文が活きる場面
OpenESに書く文章の中で、ときには自分の“話すことへの苦手意識”を正直に表現してもOKです。
たとえば、
私は人前で話すことが得意ではありませんが、その分、相手の立場をよく考えて行動するよう意識しています。
発言よりも、周囲の状況を見て動くことにやりがいを感じています。
このように、“できないこと”をそのまま書くのではなく、だからこそ”育った力”とセットで伝えることで、
マイナス印象どころか、「自分を客観視できる人」という評価につながることもあります。
無理に話せるふりをするよりも、自分らしく書く方が、ずっと説得力があります。
まとめ:OpenESは、コミュ障の“静かな逆転チャンス”
OpenESは、たしかに文章だけで勝負する分、“話すのが得意な人”が有利に見えるかもしれません。
でも、採用担当として多くのESを読んできた立場から言えば、本当に印象に残るのは、「話せる人」より「自分をよく理解している人」です。
- 苦手を無理に隠さず
- 等身大の自分を整理し
- 誠実に言葉を選んで書く
この3つさえできていれば、OpenESは“話せない人”こそ活かせるツールになります。
私自身、就活では会話力に引け目を感じ続けていました。
ですが、OpenESの文章で「落ち着いた思考が伝わってきた」と言われたとき、初めて「このままでもいいんだ」と思えました。
面接で緊張しても、うまく話せなくても、OpenESで“あなたらしさ”を先に届けることができれば、それが安心材料になります。
苦手を隠すのではなく、変換して武器にする。
その第一歩として、OpenESは“静かな逆転チャンス”です。
OpenESで伝えた内容を再利用して、面接でもうまく伝えたい方はこちらもおすすめです。
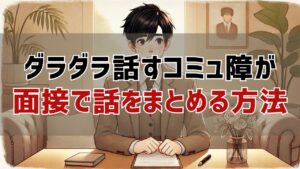
「話がまとまらない」を回避するコツを解説しています。