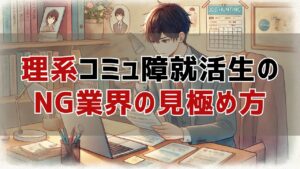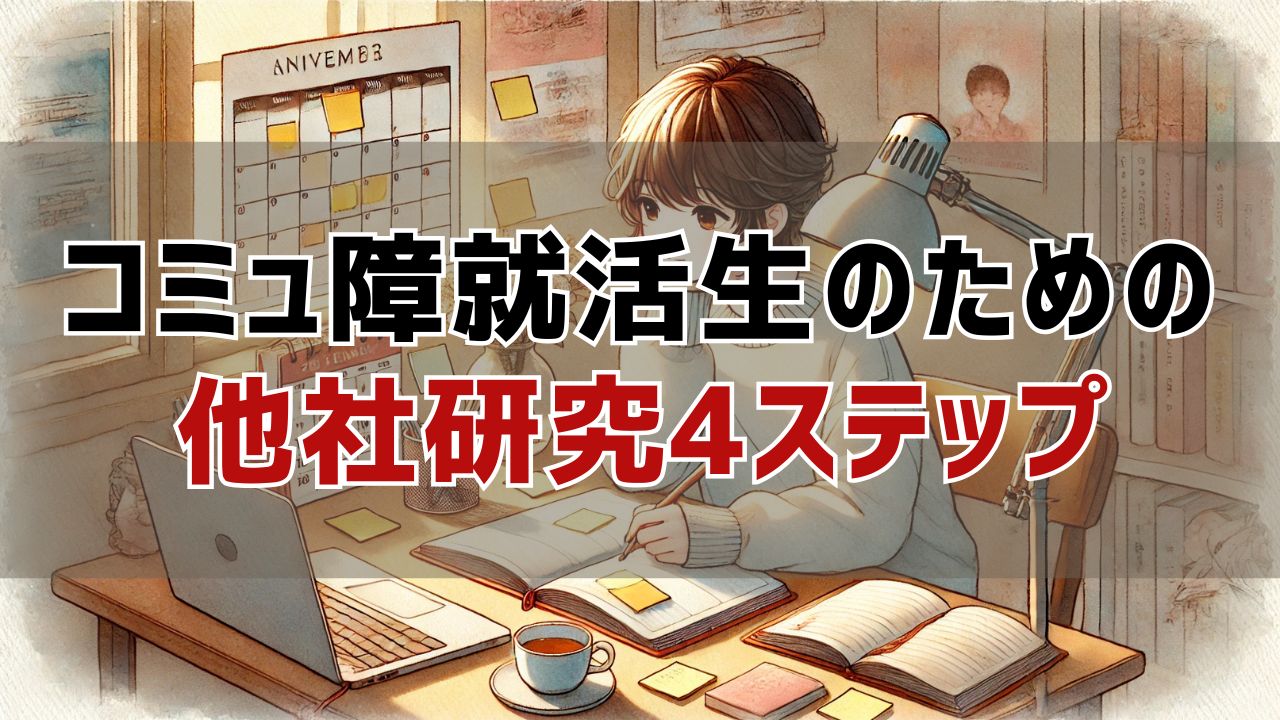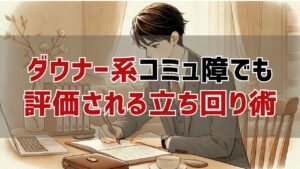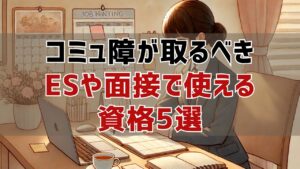「面接で“他社との違い”を聞かれたらどうしよう…」
この質問、コミュ障気味の就活生にとってはかなりのプレッシャーですよね。
私も面接でこの質問をされて、言葉が出ずに頭が真っ白になったことがあります。
この記事では、かつて「話せない自分」に悩みながら就活をした私が、実際にやってよかった他社研究のやり方・考え方・答え方をまとめました。
- 話すのが苦手な就活生でもできる、他社研究のステップ
- 面接で「他社との違い」を聞かれたときの安心フレーズ
- 志望動機に深みを出すための、比較の考え方
- 比較が苦手な人がやりがちなNGパターンとその避け方
「他社と比較なんて無理」「自分の言葉で語れない」そんな不安を持つあなたに向けて、無理をしなくても戦えるやり方を、具体的にお伝えしていきます。
コミュ障が他社研究を行うメリットは何?
「話すのが苦手だから、他社との違いなんて語れない…」と感じている人にこそ、他社研究はぜひやってほしい準備のひとつです。
というのも、他社研究=“話すためのネタ”をストックする作業だからです。
しかもこのネタは、話し方や表現力よりも、“自分がどう感じたか”をベースにできるので、コミュ障でも十分戦えます。
ここでは、他社研究をすることで得られる具体的なメリットを3つ紹介します。
メリット①:志望動機に「自分なりの言葉」が加わる
エントリーシートや面接で求められる志望動機というと、
「御社の理念に共感しました」
「成長できる環境があると思ったからです」
といったテンプレ的な表現に頼ってしまいがちですが、他社と比較して見つけた“自分だけの気づき”があると、一気にオリジナル感が出ます。
たとえば私自身、「同じ業界でも、御社は“穏やかな対話を大切にしている”という印象を受けました」と伝えたことで、「ちゃんと見てくれてるんだな」と面接官に言われたことがあります。
これは難しいことではなく、感じたことを自分の言葉でまとめるだけでOKなんです。
関連記事
他社との違いを感じても「浅い話になってしまう…」と悩む方には、“深みのある伝え方”を紹介したこちらの記事も参考になります。
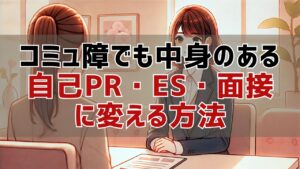
メリット②:面接で「他社との違い」を聞かれても焦らず答えられる
この質問、想像以上に多くの企業が聞いてきます。
しかも、話すのが苦手な人にとっては「比較なんてできない…」と焦るきっかけになりやすいですよね。
でも、事前に“相性”ベースで他社研究をしていれば、
「この会社の〇〇は落ち着いていて自分に合う」
「他社の□□は少しテンポが早すぎて戸惑った」
など、優劣ではない視点で答える準備ができます。
自分の感じたことに基づく答えは、たとえ言葉がシンプルでも伝わります。
むしろ表現が凝っていないほうが、嘘っぽくならず好印象です。
メリット③:受ける企業に納得できて、面接の緊張が和らぐ
コミュ障にとって最大の敵は「緊張」です。
でも、不思議なもので、「なんとなくこの会社の方が安心できる」と思えるだけで、面接前の緊張の度合いが全然違ってきます。
私も、「この会社の人たち、話しやすそう」と思えた企業では、事前に気持ちが落ち着いて準備もスムーズでした。
その裏には、他社と比べたときに「ここが自分に合ってる」と納得できた安心感があります。
コミュ障就活生のための他社研究の進め方4ステップ
「他社研究って、どうやって進めればいいの?」という疑問に、シンプルかつ無理のないやり方でお答えします。
コミュ障就活生にとっては、「言葉」より「感覚」や「安心感」が大事です。
だからこそ、企業の理念や数字を見る前に、「自分にとって合いそうかどうか」を基準に進めていく方法が向いています。
ここでは、実際に私が行っていた4ステップを紹介します。すべてやっても30分程度で終わるシンプルな内容です。
ステップ①:社員紹介・雰囲気・価値観をざっくり書き出してみる
まずは、気になった企業の「社員インタビュー」や「採用動画」をチェックして、感じたことをざっくりメモしてみましょう。
- 落ち着いた話し方の人が多い
- テンション高めで疲れそう
- 社員の人が笑いながら話していて安心感があった
など、具体的なデータではなく、“雰囲気”をメモするのがコツです。
この段階では、正確な情報や比較は気にしなくて大丈夫です。
むしろ「ふわっとした印象」だからこそ、自分の感情に素直になれます。
ステップ②:「違い」ではなく「違和感のなさ」で整理する
企業研究というと、「A社は成長重視、B社は安定志向」といった“違い”を言葉で並べがちですが、それよりも大事なのは、「自分が違和感なく馴染めそうかどうか」です。
たとえば、
- この会社の“体育会系”な感じは苦手かも
- 静かにコツコツ働く雰囲気が合ってそう
といった感覚をもとに、企業をいくつかに分類しておくと、自分の“合う・合わない”がはっきりしてきます。
この整理法は、言語化が苦手な人でも直感的にできるのでおすすめです。
ステップ③:「なんとなく合わない理由」をメモして比較に使う
つい「好きな会社」のことだけを考えてしまいがちですが、「ここはなんとなく違う」と思った会社の理由も残しておくのがポイントです。
私の場合、
「話すスピードが速すぎてついていけなさそう」
「全員が笑顔で話していて、自分は浮きそう」
といったことをメモしていました。
こうしておくと、面接で「他社との違いをどう感じましたか?」と聞かれたときに、優劣ではなく相性として語るネタになります。
ステップ④:「自分はこの会社なら話せそう」と感じた会社だけ残す
最終的に、「この会社なら緊張してもなんとかなる気がする」と思える会社を数社だけ選んで、そこに集中しましょう。
話すことが苦手な人にとって、受ける企業を絞ることは“甘え”ではなく戦略です。
エントリー数を増やせば増やすほど、疲弊して判断力も落ちます。
少ないチャンスを確実に活かすためにも、「話せそうな会社」だけにリソースを注ぐ。
他社研究のゴールは、「安心して受けられる会社を見つけること」だと考えてみてください。
関連記事
より深く1社を分析したい方は、「企業研究」の方法をまとめたこちらも合わせてご覧ください。

コミュ障就活生が面接で「他社との違い」を聞かれたときの答え方のフレーズは?
「他社との違いをどう感じましたか?」という質問、予想してなかったタイミングで飛んでくると、一気に頭が真っ白になりますよね。
私も最初の頃は、口ごもってしまい、「比較なんてしてません」と答えて撃沈したことがあります。
でも大丈夫。
この質問は“言葉巧みに話す力”を見ているわけではありません。
企業が見ているのは、「自分なりに考えて選んでいるか」「納得して応募しているか」という“思考の深さ”です。
そこで、コミュ障でも答えやすい3つのフレーズ例と、使いやすくするためのポイントを紹介します。
フレーズ例①:「他社は◯◯に力を入れていますが、自分には少し合わないと感じました」
この言い回しは、他社を否定せずに、自分との相性の違いを表現できるので、使いやすく安心です。
たとえば、
他社はスピード感や成果主義を大事にされていましたが、自分には少しプレッシャーが大きく感じられました
というように、自分の性格や働き方の希望と照らし合わせて話せば、立派な“比較”になります。
フレーズ例②:「説明会で感じた△△の姿勢に、自分も共感できたため志望しています」
比較を直接言わずに済む便利なフレーズです。
「他社ではなく御社を選んだ理由」を、“説明会で感じた雰囲気”などに落とし込むことで、自然な会話になります。
たとえば、
説明会で社員の方が“まずは話を聞く姿勢を大切にしている”と話していたのが印象的で、自分の考え方とも近いと感じました
と伝えれば、「なぜここに応募したのか?」が十分伝わります。
フレーズ例③:「御社の□□という考え方が、自分の価値観と近いと感じています」
これは「他社は〜」という比較をしないパターン。
それでもしっかりと「自分で企業を見比べて考えた」印象を与えることができます。
御社の“じっくり育てる文化”が、自分のペースを大事にしたいという考え方と近いと感じました
のように、価値観の近さを語ることで、言葉に詰まらず安心して話せます。
ポイント:優劣ではなく「相性」で比較するのが安心
比較でよくあるミスは「御社の方が優れている」「他社は劣っている」といったニュアンスを出してしまうこと。
でも、そういう言い方はリスクが高いです。
他社を下げて自社を上げるより、「自分に合うから御社を選んだ」という相性軸の方が、自然で角が立ちません。
詰まりそうなら「◯◯に違和感があって、御社ではそれがなかった」とだけでもOK
どうしても言葉が出てこなかったときのために、使える“お守りフレーズ”です。
たとえば、
他社では全員がスピード重視で進める印象があり、少し違和感がありました。
御社は一人ひとりの丁寧な動きが印象的で、自分にはそちらの方が合うと感じました
このように、「違和感→安心感」という流れで話すと、落ち着いて言葉が出てきやすくなります。
コミュ障がやりがちな他社研究での比較NG例
他社研究を頑張っているつもりでも、やり方を間違えると逆に「違いがうまく話せない…」と自信をなくしてしまうことがあります。
特に、比較や分析が苦手な人ほど、「それっぽい言い方」を求めすぎて不自然になってしまうことが多いです。
ここでは、私自身がやってしまった失敗もふまえて、コミュ障就活生がついやりがちなNG比較例を紹介します。
NG① 条件・知名度など“表面的な違い”ばかり挙げる
「給料が高い」「福利厚生が手厚い」「有名企業」などのポイントは、もちろん大事です。
でも、それだけを比較に使うと、「どこの企業でも言える話だな」と見抜かれてしまいます。
たとえば面接で、
御社は安定していて、福利厚生が整っているので…
と答えると、「それ、他社でも言えるよね?」と内心思われて終わることもあります。
表面的なスペックではなく、「雰囲気」「価値観」「話しやすさ」など、内面的な軸を加えることが大切です。
NG② 他社を下げて評価するような言い回しをする
「他社は◯◯がダメだったので…」という言い方は避けましょう。
採用担当者は意外と“謙虚さ”や“言葉選びの丁寧さ”も見ています。
私も一度、「説明会で偉そうに話してる社員がいてちょっと…」と本音を出してしまい、面接官の表情がピタッと止まったことがあります。
これは完全に失敗でした。
他社を悪く言わなくても、「御社が自分に合う」と伝えるだけで、比較は成立します。
NG③「なんとなく雰囲気が良さそう」だけで終わらせてしまう
「なんとなく」
「雰囲気がいいと思った」
これはよくある回答ですが、これだけで終わると、根拠が弱く伝わりません。
逆に、こう言い換えると一気に印象が変わります。
説明会の中で社員の方が“困ったときはすぐ相談できる”と言っていたのが印象に残り、自分も働きやすそうだと感じました
「雰囲気が良さそう」という感覚に、具体的な理由を1つ加えるだけで、説得力がグッと増します。
NG④ どこの会社にでも言えるような表現をしてしまう
たとえば、
- 風通しがよさそう
- 成長できそう
- チャレンジできる環境
こういった言葉は便利ですが、あまりに抽象的で、“誰にでも言ってるように見える”危険性があります。
私も就活初期はテンプレばかり並べて、「中身が伝わってこない」と言われたことがありました。
「なぜそう感じたのか」という背景や具体エピソードを添えるだけで、表現は同じでも“自分の言葉”になります。
まとめ:他社との違いが言えないのは悪くない。自分の軸を持って話そう
他社研究において、特にコミュ障気味で言葉に自信がない就活生にとっては、比べることより“自分が持っている感覚をうまく伝えること”の方が、はるかに難しい。
でも大丈夫です。
他社と明確な差を説明できなくても、「自分はこの会社の空気感が合っていた」と思えたなら、それだけで立派な理由になります。
就活はプレゼンじゃありません。
優れた言葉や完璧な比較よりも、「納得して選んだ」という姿勢こそが伝わるべきことです。
話せないことに悩むのではなく、“話せる会社を見つけること”に力を使う。
他社研究は、まさにそのための手段です。
言葉にしきれない感覚を、大切な判断基準として扱ってあげてくださいね。
業界研究についてはこちら