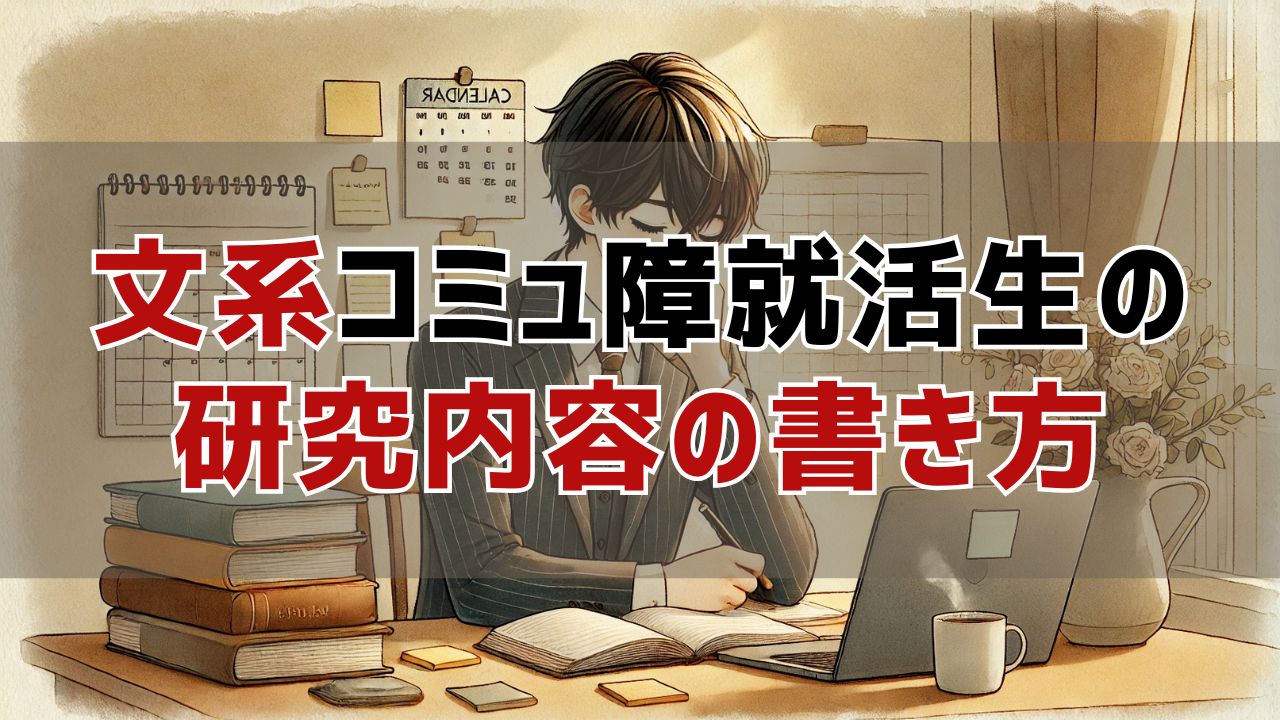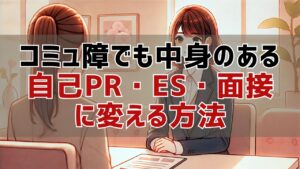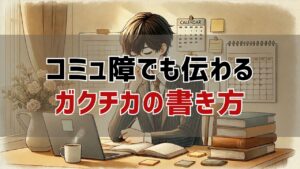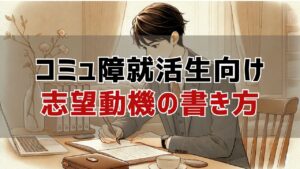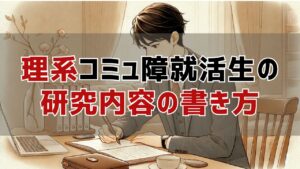「研究内容なんて、文系だし大してやってない…」
「ゼミもそこまで本格的じゃなかったし、書くことがない…」
そんなふうに悩んでいませんか?
特に、コミュ障気味で“言葉にして説明する”ことに不安がある人にとって、研究内容の記述はESでも面接でも大きなハードルになる部分です。
でも安心してください。文系の研究内容は、“テーマっぽく見せる工夫”と“考えた過程の言語化”で、十分に書けます。
この記事では、元・話すのが苦手だった就活生、そしてその後採用担当として学生のESを見てきた立場から、
- 研究内容がなぜ求められるのか
- 研究テーマがない人でも書けるアレンジ方法
- コミュ障でも使いやすいテンプレと例文
- 書けない・話せないときの対処法
を、実用的にまとめました。
なぜ文系でも研究内容が聞かれるのか?
「文系だし、理系みたいに実験も分析もしてないのに…」
そう思って、研究内容の記入欄に困っている人は少なくありません。
でも、採用担当としての視点で言うと、企業が研究内容を聞く目的は“学術的な深さ”ではありません。
特に文系の場合、「何を学び、どう考え、どう取り組んだか」を知るためのきっかけとして研究内容を使っていることがほとんどです。
ここでは、なぜ文系でも研究内容を聞かれるのか、その背景を2つの視点から解説します。
「学ぶ姿勢」や「論理的思考力」を見るため
研究テーマそのものよりも、「そのテーマをどう選び、どう掘り下げたか」に注目している企業は多いです。
これはつまり、“考える力”や“物事への向き合い方”を見ているということ。
たとえば、「授業で扱った社会問題についてゼミで深掘りした」という話でも、
- どうしてその問題に興味を持ったのか
- どんな視点で情報を集めたのか
- 議論の中でどんな気づきがあったのか
といった要素が含まれていれば、“研究内容”として十分評価されます。
面接でも、「話が論理的に組み立てられているか」「テーマに主体性を持っていたか」が見られることが多く、研究の“完成度”をチェックしているわけではないのです。
面接での話題づくりや深掘り材料として活用されるため
企業側にとって、研究内容はあなたという人物の考え方や興味関心を知るための導入トピックでもあります。
「研究内容から話が広がると、面接がしやすくなる」と感じている面接官は多く、特に口下手な就活生に対しては、最初に研究テーマを出してもらうことで“話しやすい空気”をつくる狙いもあります。
私自身も面接で、研究内容をきっかけに好きな本や社会問題の話に広がり、話すペースをつかめた経験が何度もありました。
文系でも研究内容が求められる理由は、「深さ」や「専門性」を見るためではありません。
あなたがどう考え、どう向き合ったかを知るためのヒントとして見ているということを、まずは理解しておきましょう。
研究テーマがないコミュ障文系学生でも書ける3つのアレンジ法
「ゼミもゆるかったし、研究なんてしてない…」
「卒論のテーマすらまだ決まってない…」
そんな状況で「研究内容を書け」と言われても、困りますよね。
でも、実際には“研究っぽく見せる”工夫をすれば、しっかりESに書けます。
ここでは、研究内容がない文系学生でも使える3つのアレンジ方法を紹介します。
アレンジ①:ゼミで扱ったテーマを“研究風”に言い換える
ゼミの活動がゆるくても、扱ったテーマを「問い」「視点」「調べ方」などに置き換えるだけで、“研究風”に整います。
Before
高齢社会における介護制度についての文献を読み、ディスカッションを行った
という活動の場合を考えます。
After
高齢社会における介護制度の課題を、政策比較という視点で検討した
というように書き換えるだけで、グッと研究っぽく見えます。
重要なのは、どんな切り口でそのテーマに関わったかを明確にすること。難しい言葉で書く必要はありません。
アレンジ②:課題レポートや卒論計画をもとに書く
ゼミに入っていない、活動もしていない…という人でも、授業で出したレポートや、卒論で考えているテーマの“予定”を使ってOKです。
Before
授業で書いたレポートでは、フェイクニュースの拡散とSNSの関係について調べました。
という取り組みも言い方を変えられます。
After
情報リテラシーの観点から、SNS上でのフェイクニュース拡散の要因を分析しました。
とすれば、十分に研究テーマになります。
卒論は“構想段階”でも問題ありません。
「今後、こういうテーマで調べる予定です」という形でも、興味・関心や思考の方向性は伝えられます。
アレンジ③:「個人の興味関心」を研究っぽく見せる工夫
趣味や日常の関心から発展させたテーマも、工夫次第で“研究”として見せられます。
たとえば、私は大学時代にあるテレビ番組をきっかけに「日本と海外の報道姿勢の違い」に興味を持ちました。
そして、そこから記事を集めて比較したことがあります。
これは完全に趣味でしたが、
報道における“語り方”の違いが、視聴者の印象形成にどのように影響するかをテーマに、複数国のニュース番組を比較・分析しました。
というように書いたところ、しっかりと“研究内容”として受け取ってもらえました。
「何を扱ったか」より、「どう取り組んだか」の方が評価されやすい。
それが文系就活の特徴でもあります。
関連記事
「そもそも書けることがない…」と感じる方には、OpenES全体をどう埋めるかの視点から考えるこちらの記事もおすすめです。
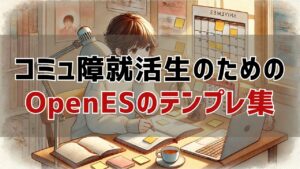
文系コミュ障でも伝わる研究内容のES構成テンプレ
話すのが苦手な人にとって、ES(エントリーシート)の文章は「しっかり準備すれば伝えられる」数少ない勝負の場です。
とはいえ、研究内容をどうやって構成すればいいかわからない…という人も多いはず。
そんなときに役立つのが、シンプルかつ順序立てて書けるテンプレートです。
以下の5つのパートに分けて書けば、「伝わる文章」になります。
1. 結論:どんなテーマを扱ったか
まず最初に、「○○というテーマに取り組みました」と簡潔にテーマを述べます。
私は、SNSにおける情報の信頼性について研究しました
ここでカッコつけた表現は不要です。
わかりやすさが優先です。
2. 理由:なぜそのテーマを選んだか
次に、そのテーマに興味を持った理由を説明します。“身近な問題意識”から始めると、自然な流れになります。
大学の講義でフェイクニュースの事例を知り、日常的に使っているSNSでも同じような影響があるのではと疑問を持ったためです
3. 方法:どのような調べ方や視点で取り組んだか
どんな資料を使ったのか、どう比較・分析したのかを簡潔に説明します。
複数の報道記事やSNS投稿を収集し、情報の出所や反応の違いを比較しました
文系で実験がなくても、“どう調べたか”“どう見ようとしたか”を書けばOKです。
4. 学び:そこから得た考え方や変化
ここが一番大事です。「だから何を感じたか」「どう考えが変わったか」を書きます。
情報は内容だけでなく、“誰がどう伝えるか”で受け手の印象が大きく変わることを実感しました
考え方や感じたことの変化を書くことで、あなた自身の思考力が伝わります。
5. 展望:その経験をどう活かしたいか
最後に、この研究経験をどのように社会や仕事に活かしたいかを軽く触れて締めましょう。
今後は、相手に伝わる言葉選びや表現の工夫を意識しながら、丁寧な情報発信ができる人になりたいと考えています
話を未来につなげることで、前向きな印象になります。
この5ステップに当てはめるだけで、話すのが苦手な人でも書きやすく、相手に伝わりやすい構成になります。
関連記事
ESでは伝えられても、面接で話すのが苦手な方はこちらの記事で「焦らず話すための型」を知っておくと安心です。
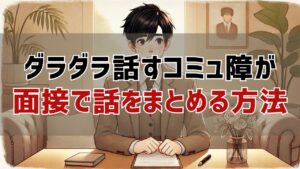
例文|文系コミュ障就活生のための研究内容サンプル
ここでは、実際に使える「研究内容」記述の例文を3パターンご紹介します。
「ゼミもゆるい」「卒論まだ決まってない」「そもそも研究って何?」という人でも、書き方を工夫すればしっかり伝わるESが作れます。
それぞれ、テンプレに沿って構成されています。
例文①:ゼミでの社会問題研究を題材にした例文(簡潔型)
私は、地方における若者の人口流出について研究しました。
地元の活性化に関心があり、ゼミで地方創生をテーマに扱ったことがきっかけです。
主に政府の政策資料や自治体の取り組み事例を調べ、比較分析を行いました。
地方によって課題の背景が異なることを知り、「一律の支援では届かない」という視点を持つようになりました。
今後は、相手の状況を丁寧に理解しながら関わる姿勢を仕事にも活かしたいと考えています。
話すのが苦手でも、しっかり構成されていれば文章で伝わりますよ。
例文②:卒論未着手の人向け(予定ベース)
私は現在、「SNSと若者の自己表現」をテーマに卒業論文の準備を進めています。
情報社会の中で、若者がどのように自分を表現しているかに興味を持ったのがきっかけです。
今後はアンケートや投稿分析などを通じて、自己表現の特徴や傾向を調べる予定です。
このテーマを考える中で、「相手にどう見られるか」を意識する心理に強く関心を持つようになりました。
将来は、相手視点に立ったコミュニケーションを心がけていきたいと思っています。
「予定」でも問題ありません。思考の軸が伝わればOKです。
例文③:趣味・個人関心から展開するタイプの研究内容
私は、テレビ報道における言葉の使い方が、視聴者の印象にどのような影響を与えるかについて調べました。
報道番組を見る中で、同じ事件でも言葉の選び方や語調によって受ける印象が大きく異なることに気づいたのがきっかけです。
異なる報道番組で使われた表現を記録し、比較するという方法で分析を行いました。
この経験から、伝え方一つで相手の受け止め方が変わることを実感しました。
今後は、正確に伝える力だけでなく、相手の立場を考えた発信を意識したいと考えています。
“趣味ベース”でも、伝え方次第で立派な研究内容になりますよ。
【コミュ障向けの対処法】書けない・話せないときはどうする?
「構成も分かったし、例文も読んだけど…やっぱり自分には書けない」
「面接で研究内容を聞かれたら、たぶん頭が真っ白になる…」
そんなふうに感じている人もいると思います。
私自身、最初はESの“研究内容欄”を見るだけでプレッシャーを感じていましたし、面接では言葉が詰まってしまって何も伝えられなかったこともあります。
でも、そういうときに役立ったのが、「書けないときの整理術」と「話せないときの捉え方の転換」でした。
書けないときの工夫:5W1Hで無理やりメモにして整理する
文章にしようとすると手が止まる…という人は、まず5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どうやって)に分けてメモしてみましょう。
たとえば、こんな風に箇条書きにするだけでOKです。
- いつ:大学3年の前期ゼミで
- どこで:社会学の授業の一環で
- 誰が:自分とゼミ仲間で
- 何を:都市部と地方の雇用問題について
- なぜ:格差問題に関心があったから
- どうやって:資料を集めてディスカッションした
これをつなげれば、それなりに自然な文章になりますし、「とにかく手を動かす」ことで考えが整理されていきます。
話せないときの工夫:「研究内容=取り組んだ姿勢」と捉える
面接で研究内容を聞かれても、テーマの立派さや分析の深さを披露する必要はありません。
話すのが苦手な人にとっては、「研究内容=自分なりに取り組んだことの例」くらいに思っておくと気がラクになります。
たとえば、
テーマとしては浅いかもしれませんが、社会問題に興味を持ち、自分なりに考えることを大切にしました
といった前置きを入れるだけでも、十分に“取り組む姿勢”は伝わります。
元面接官としても、「立派な研究をしている人」より「不器用でも自分の言葉で話そうとしている人」に好印象を持ったことは何度もありました。
自信がないときほど、「どう見せるか」より「どう向き合ったか」に目を向けることが、コミュ障就活の強い味方になります。
まとめ|内容より“取り組む姿勢”を伝えよう
文系で、しかもコミュ障気味だと、「研究内容なんて自分には無理だ」と感じてしまいがちです。
ゼミの内容も浅いし、そもそも研究って呼べるほどのことをしていないと思う人も多いです。
でも、就活で求められているのは、専門性の高さや華やかなテーマではなく、「どう向き合ったか」「どう考えたか」という姿勢です。
たとえテーマが地味でも、考え方や取り組み方がしっかり伝われば、それだけで十分に評価されます。
- 話すことが不安なら、書くことで丁寧に伝える。
- 内容に自信がないなら、考えたプロセスを大切にする。
コミュ障だからこそ、言葉を選び、伝える順番に気を配り、丁寧に準備すればOKです。
あなたの取り組んできたこと、ぜひ“あなたの言葉”で表現してみてください。
これなら書けそう」と思える1文から、就活は一歩ずつ前に進んでいきます。
文系コミュ障就活生の業界研究のポイントは以下の記事でまとめています。