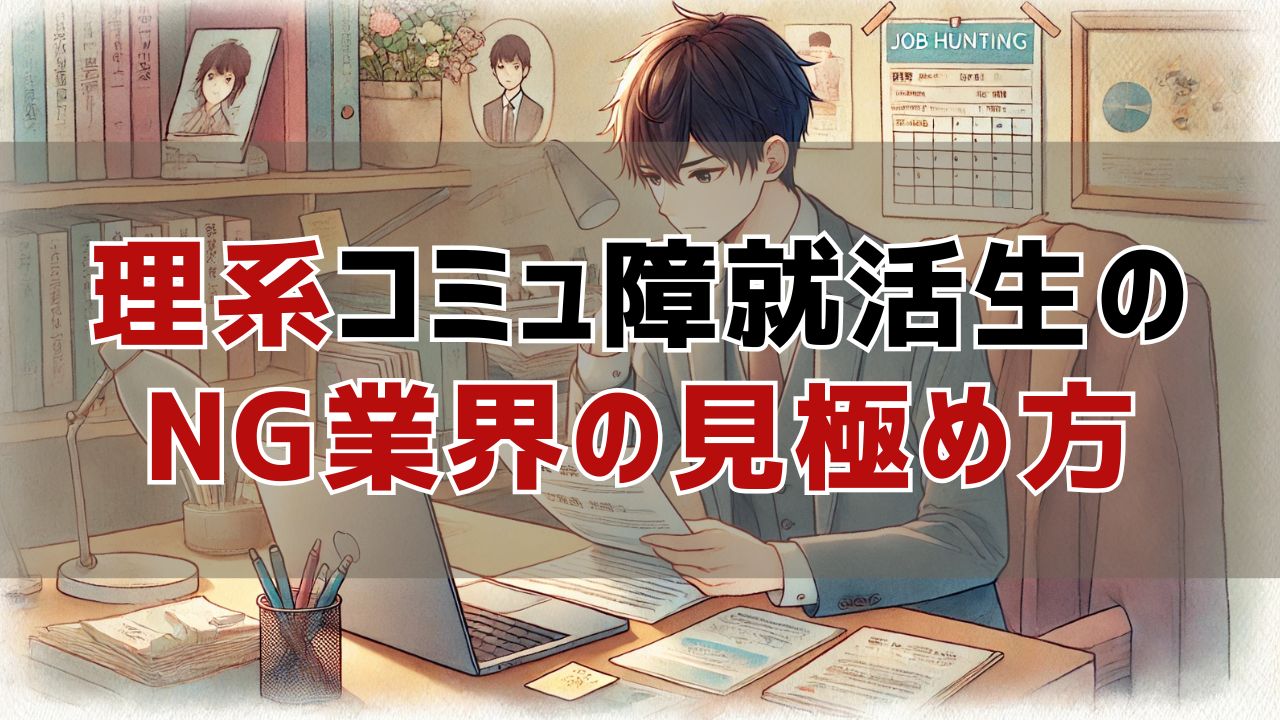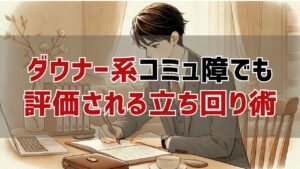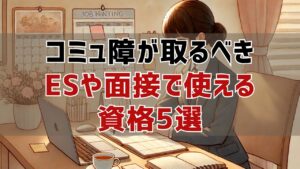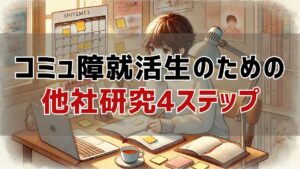「話すのが苦手な自分が、どこで働けるのか想像できない」
「技術はやってきたけど、就活でどう伝えればいいかわからない」
理系の就活では、研究内容や専門性が重視される一方で、面接や職場選びでは“話す力”や“空気を読む力”が暗黙のうちに求められる場面も多くあります。
私自身、研究室では集中して作業に打ち込めたのに、就活では集団面接や座談会で何も話せず、落ち込む日々を過ごしました。
でも、後に面接官として多くの理系学生を見てきて気づいたのは、「話すのが苦手でも、向いている環境ならちゃんと評価される」ということです。
逆に言えば、「どの業界を選ぶか」で、その後の働きやすさや面接突破率まで大きく変わります。
このページでは、
- なぜ理系のコミュ障こそ業界研究が重要なのか
- 避けた方がいい業界・職種の特徴
- 自分の研究や性格を活かせる業界の見つけ方
- 「職場の空気感」を調べるための方法
- 配属ガチャのリスクを減らす業界選びの工夫
などを、元・理系コミュ障就活生+元面接官の視点からリアルに解説していきます。
理系のコミュ障就活生が業界研究をするメリット
理系の学生は「研究内容」や「専攻との関連性」が重視されがちです。
しかし、実際の就活ではそれ以上に、「どんな職場でどんな人たちと働くのか」という“環境との相性”が重要になります。
特に、話すのが苦手なタイプの理系学生にとって、業界研究は技術力以外の不安を和らげる武器になります。
ここでは、元・理系コミュ障就活生だった自分自身の経験と、元面接官として学生を見てきた立場から、業界研究をやるメリットを3つに分けてお伝えします。
面接やESで“技術以外の話”ができない不安を減らせる
私自身、就活初期のESや面接で「志望動機」や「自己PR」に苦戦していました。
専門性については話せるけど、それ以外の質問になると黙ってしまう。
「どうしてこの業界に?」と聞かれても、「なんとなく…」としか答えられず、面接が終わった瞬間に後悔していました。
でも、業界研究を進めていく中で、
「自分はこういう働き方が合っている」
「こういう社風の職場なら安心して働けそう」
という納得感のある理由が増えていくと、それがそのまま“自分の言葉で語れる志望動機”になっていきました。
面接での会話に自信がない人ほど、事前に“業界軸”を持っておくことが、自分を助けてくれます。
配属ミスや“想像と違った職場”を避けるための防衛線になる
理系職の怖さは、いわゆる“配属ガチャ”にあります。
内定後、「技術系だから大丈夫」と思っていたら、実際は
- 外回りの技術営業
- ヘルプデスク寄りの社外対応SE
- 実験ではなく品質管理の事務作業
といった、想像していた仕事と違うポジションに配属されてしまうケースも少なくありません。
面接官として企業側にいたときも、「幅広く活躍してほしい」という名目で、入社後に想定外の配属をするケースは実際にありました。
だからこそ、業界や企業がどんな配属傾向を持っているかを、業界研究の段階で把握しておくことが“自分のキャリアを守る防衛線”になります。
「研究内容を活かせる企業」を見つける指針になる
理系学生の強みのひとつが、研究で培った専門知識やスキル。
ただし、それをどこで活かせるかを知らないままだと、「自分のやってきたこと、何だったんだろう…」と感じてしまいがちです。
業界研究を通じて、
- 自分の研究がどの業界・企業で活かされているか
- どんな職種なら専門性が求められているか
- 同じようなバックグラウンドの人がどう働いているか
といった情報を知っておくことで、“知識を活かせる職場”という観点で企業選びができるようになります。
これは、面接で話す際にも非常に説得力がある材料になりますし、企業からも「よく調べている」と評価されやすくなります。
「話すのが苦手だからこそ、準備で差をつける」
それが、理系コミュ障就活生の業界研究における最大の価値です。
理系コミュ障が避けたい業界の特徴
話すのが苦手な理系学生にとって、就活で一番怖いのは「入ってみたら想像以上に“話す仕事”だった」というギャップです。
私自身、技術職なら安心だと思い込んで応募した企業で、面接中に
「お客様と直接やり取りしてもらいます」
「将来的には営業も視野に」
と言われ、頭が真っ白になったことがあります。
また、面接官として働いていたときも、「この学生、技術力はあるのに、職場に合わなかったらしんどくなるだろうな…」と感じた場面は何度もありました。
ここでは、理系コミュ障の就活生が避けたほうがいい業界・職種の特徴を3つに絞ってお伝えします。
特徴①:年功序列・声が大きい人が得をする会社
「技術力」よりも、「体育会系のノリ」や「飲み会での盛り上げ力」などが評価されがちな企業文化の職場があります。
このような職場だと、コミュ障気質の人にとってストレスが溜まりやすい環境です。
特に古い体質のメーカーや大企業では、
- 年次がすべてを決める
- 声が大きい人がリーダーになりやすい
- 論理よりも“現場の空気”が重視される
といった風潮がまだ残っていることもあり、「物静かに地道に取り組むタイプ」は評価されづらい傾向があります。
OB訪問や説明会などで、「役職者の年齢構成」や「社員紹介の雰囲気」に注目すると、そうした文化の有無が見えてきます。
特徴②:技術営業・SE系など話す業務が多い職種
「技術職募集」と書かれていても、よく中身を見ると実際は“お客様とのやり取りがメイン”の職種であることも多々あります。
たとえば、
- 技術営業(プリセールス、フィールドエンジニアなど)
- 社外SE(顧客折衝が多い開発案件)
- ITコンサルや提案型インフラ導入職
こういった職種は、資料作成や技術提案といった要素があっても、基本的には“会話で関係性を築く”仕事です。
話すのが苦手なまま無理に挑戦すると、仕事の本質とのギャップに苦しみます。
特徴③:「幅広い活躍を期待」と書かれている=配属ガチャ注意
一見するとポジティブな表現ですが、「幅広いフィールドで活躍してもらう」「多様な部署で経験を積んでもらう」といった文言には注意が必要です。
この手の表現がある企業では、
- 研究開発志望で入社しても、生産管理や営業に配属される
- 本人の希望より「会社都合」の配属が優先される
- 面接で希望職種を話しても「うちは総合職だからね」と濁される
といったケースが実際にあります。
私が面接官だったころも、「開発を希望」と書いていた学生が、入社後に工場のライン管理に配属されて戸惑っていた例を見ました。
コミュ障気質のある理系学生にとっては、「想定外の仕事への切り替え」が大きなストレスになるため、こうした“総合職前提”の企業は避けた方が安全です。
「理系=技術系=安心」ではないということを前提に、仕事内容だけでなく、“働き方と社風”も含めて業界を見極めていくことが大切です。
業界研究で“志望軸”が見えてきたら、次はそれを志望動機や自己PRにどう落とし込むかも重要です。
書き方のコツはこちらの記事で詳しく解説しています。
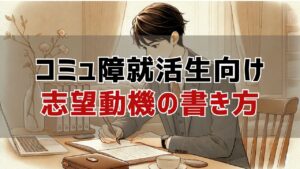
理系コミュ障におすすめの業界・職種
「避けるべき業界はわかったけど、じゃあ自分はどこを目指せばいいの?」
そう思う方も多いかもしれません。
私自身、面接が苦手で会話に自信がなかった頃、「このままだとどこにも行けないんじゃないか」と思い詰めていた時期がありました。
しかし、“話す力ではなく、観察力や分析力、集中力が求められる環境”を選ぶことで、就活にも少しずつ手応えを感じられるようになったのです。
ここでは、元コミュ障理系就活生、そして元面接官の視点から、会話に苦手意識があっても働きやすく、かつ評価されやすい職種・業界を3つ紹介します。
実験・分析系:医薬・食品・材料開発など
この分野は、黙々とデータを取る、装置を操作する、分析ソフトで結果を読み取るといった“一人でコツコツ進める作業”が中心です。
- 医薬品の成分分析
- 食品の品質試験
- 材料の物性評価
こうした職場では、「正確性」や「観察眼」が重視され、会話のうまさよりも“丁寧な作業姿勢”や“ミスを防ぐ工夫”が評価される傾向があります。
面接でも、「自分のペースで正確に仕事を進めるのが得意」といった自己PRが響きやすく、無理に明るく振る舞わなくても良い空気感の企業が多いです。
研究開発系:学部内容に近い内容で選ぶと安心
「自分の研究テーマに近い分野の会社」を選ぶことで、会話が苦手でも“研究内容を軸に”説明しやすくなります。
例えば、自分が材料化学を専攻していたなら、
- 化学メーカーのポリマー開発
- 電子材料の特性改善
- セラミック素材の応用研究
といった業務に絞って企業を探すと、「専門分野がつながっている安心感」が生まれます。
元面接官としての経験でも、「話し方がたどたどしくても、内容に一貫性がある学生」は説得力があり、評価されていました。
“自分が話しやすい内容”を軸に職場を選ぶことは、立派な戦略です。
自分の研究テーマをうまく活かして志望動機やESに書きたい方は、こちらの“研究内容の書き方ガイド”もぜひご覧ください。
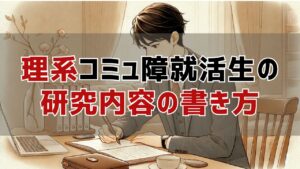
社内SE・データ分析系:静かで論理重視な環境が多い
システム保守やデータ分析、社内ツールの改修などを行う社内SE職は、基本的に内向きのやりとりが多く、コミュニケーションも論理的で落ち着いています。
- チャットやメール中心のやり取り
- 定型業務が多く、作業の再現性が重視される
- 静かな環境での長時間作業に適している
また、データ分析や機械学習モデルの構築といった業務も、発言力よりも“根拠のある仮説”や“丁寧な検証”が重視されるため、準備型・思考型の人には向いています。
私が採用面接で評価した学生の中にも、「会話はゆっくりでも、ロジックが明確で、検証手順を丁寧に話せる」タイプが多くいました。
「明るくハキハキ」より、「丁寧で一貫性のある話し方」こそ、理系職種では評価される場面がたくさんあります。
コミュ障だからといって諦める必要はありません。
“無理に話さずとも伝わる職種”は、確実に存在しています。
理系コミュ障就活生でもできる業界研究3ステップ
「業界研究って、何を調べればいいのかよくわからない」
「情報を見ても、“自分に合っているか”が判断できない」
そんなふうに感じている人は多いと思います。特に、会話が苦手な人にとっては、説明会でのグループワークやOB訪問もハードルが高く感じがちです。
私自身も、就活初期は「企業サイトを読んでメモを取るだけ」で止まっていました。
でも、“職場の空気感”や“配属される現場の実情”を先に知っておくだけで、緊張感が大きく下がることを経験しました。
ここでは、話すのが苦手でも実践しやすい、業界研究の3ステップを紹介します。
ステップ①:事業内容より「職場の様子」に注目
理系就活生はつい、「事業内容」や「技術領域」ばかりに目を向けがちです。
しかし、職場の雰囲気や働く人の姿勢のほうが、実際の働きやすさには直結します。
- 社員インタビューでの受け答えのトーン(落ち着いているか)
- 工場・研究所の動画があるか(静かか、活気があるか)
- オフィスの様子が確認できるか(開放的 or 静かに仕切られているか)
「誰と、どんな雰囲気の中で働くのか」を見る意識を持つことで、“ここなら話さなくても浮かないかも”という視点が持てるようになります。
ステップ②:社員のインタビューから“会話の圧”を感じ取る
社員インタビューの動画や記事は、話し方や表情から職場の会話テンポや文化が伝わるヒントの宝庫です。
- ゆっくりと落ち着いた話し方をしているか
- 会話の中で「無理して元気にしている感じ」がないか
- 言葉の端々に「考えて動いている人が多い」印象があるか
私が採用側にいたときも、「インタビュー動画に出ている社員の空気感」で応募する学生の傾向が変わることがありました。
落ち着いた社員が多い動画には、「自分でも行けるかも」と感じて応募してくる人が自然と集まっていたのです。
ステップ③:配属リスクがあるかをOB訪問や掲示板で確認
理系職種の就活で意外に重要なのが、「その会社は希望通りの部署に配属されやすいかどうか」です。
公式な情報では分からないことも多いですが、
- 就活掲示板(OpenWork、みん就など)の体験談
- X(旧Twitter)で「社名 配属ガチャ」などで検索
- 大学の先輩・OBに聞けるなら配属実態を尋ねる
などの方法を使って、できるだけ早い段階で“現実の配属傾向”を把握しておくことが大切です。
「技術系で入ったのに、なぜか営業に配属された」
「研究開発のはずが、工場のライン管理だった」
というケースは、事前に情報収集していれば避けられたという話も多くあります。
“静かに働ける環境か”“想定外の仕事を任されないか”を見極めることは、話すのが苦手な就活生にとって、自分を守る準備でもあります。
理系のコミュ障就活生が「この業界なら働けそう」かどうかを見極める視点
業界研究を進めても、「結局どこもそれっぽく見えてしまう」「合う・合わないが判断できない」と感じて立ち止まる人も多いと思います。
特に、会話に苦手意識がある人ほど、“何を基準に選べば安心なのか”が見えづらくなるのは自然なことです。
ここでは、元・理系コミュ障就活生として、そして面接官として多くの学生を見てきた経験から、「この業界・会社なら働けそうか」を判断するためのシンプルな3つの視点を紹介します。
自分の研究テーマが活かせそうか
話すのが苦手な人にとっては、“すでに知っている内容”をベースに説明できる状況があると、面接や入社後のストレスが大きく減ります。
自分の研究テーマと近い企業を選べば…
- 面接での会話が“知っている言葉”で進む
- 配属後の業務内容が想像しやすい
- 「なんとなく続けられそう」という安心感がある
たとえば、「高分子の研究」をしていた人なら、化学メーカーや素材開発部門を選ぶと、自分の知識がそのまま活きやすくなります。
企業研究のときは、「事業紹介」や「研究開発部の役割紹介」に、自分の研究テーマとつながるキーワードが出てくるかを探してみましょう。
毎日話す相手が“社内中心”か“社外中心”か
企業の「技術職」とひとくちに言っても、その働き方は様々です。
注目すべきは、コミュニケーションの相手が“社内”なのか“社外”なのかという点。
- 社内中心
上司、同僚とのやりとりがメイン(静かな業務多め) - 社外中心
顧客や取引先との連絡が頻繁(営業的要素が強い)
特に、「フィールドエンジニア」「技術サポート」「導入支援SE」などの職種は、“技術”と書いてあっても実際には外部との会話が多いことがあります。
会社説明会やインターン案内を見たときに、「お客様と信頼関係を築く」といった記述があれば要注意です。
「働く人の空気感」が安心できそうかどうか
最終的な判断軸として最も大切なのが、その会社で働く人たちの“空気感”が自分に合いそうかどうかです。
- 社員インタビューの口調が落ち着いているか
- SNSや動画で見る社員が「無理して明るく振る舞っていないか」
- 「自分がここに座っていたとして、疲れすぎないか」
私が面接官をしていたときも、空気が合わない会社に入ってしまった学生ほど、数ヶ月以内に苦しんでいるケースが多かったのを覚えています。
「この会社なら、話さなくても許される雰囲気がある」
そんな感覚が持てる企業を選べるようになると、就活のストレスもかなり減ります。
企業選びの正解は、“知識”より“感覚”が教えてくれることもあります。
少しでも安心できる空気を感じたら、それは立派な判断材料です。
理系就活生がやりがちなNGな業界研究のやり方
「業界研究してるつもりだけど、なぜか迷いばかり増える」
「いろいろ見たのに、どれもピンとこない」
そんな状態に陥ってしまう理系就活生も少なくありません。
特にコミュ障気質のある人は、“みんながやっている方法”が自分にはしっくりこないこともよくあります。
ここでは、私自身が就活初期にやって失敗したこと、そして面接官として多くの学生に見られた「ありがちなNGな業界研究のやり方」を紹介します。
条件で業界を決める(例:給与が高い・有名)
「年収ランキング」「福利厚生の充実度」など、数字や外見の条件で業界を決めてしまうのはよくあることです。
もちろん生活や安定も大切ですが、“職場での過ごしやすさ”を軽視すると、入社後のストレスが大きくなりがちです。
実際、私が採用側にいたときも、「高年収の企業に入りたかったけど、空気が合わなくてすぐ辞めた」という学生からの転職相談を受けることが何度もありました。
話すことに不安がある人は特に、“数字の良さ”よりも、“会話が苦手でも働きやすいか”という視点を優先することが、自分を守る選択になります。
周囲の進路に合わせる(自分の苦手が無視される)
研究室の同期や友人が受けている業界に流されてしまうのも、理系あるあるの落とし穴です。
- 〇〇さんが受けるなら安心かな
- 先生の推薦がある企業だから間違いないよね
- みんなが行ってるから自分も行かないと不安
こうした感情から、自分に合わない業界を選んでしまうと、選考でもうまく言葉が出てこなかったり、志望動機が浅くなってしまいます。
特にコミュ障の人は、「みんなが行ける場所」と「自分が行ける場所」は違うことがあると、あらかじめ理解しておくことが大切です。
私自身も、「研究室の先生に勧められた大手メーカー」の面接で、集団面接に圧倒されてほとんど話せず、不合格だった苦い経験があります。
業界研究は、「自分の価値観で選ぶための作業」です。
他人の基準ではなく、“自分が安心して働けるか”を最優先にしましょう。
まとめ|理系コミュ障の戦い方は“向いてる環境”を先に探すこと
「理系だから技術職なら大丈夫」
「話せないけど、研究の実績があれば何とかなる」
そう思って就活を始めた結果、現実とのギャップに悩む理系就活生は少なくありません。
でも大事なことは「話すのが苦手でも、環境さえ合えば十分に評価される」という事実です。
むしろ、コツコツと取り組む姿勢や、ミスのない仕事ぶり、慎重な判断力を求める職場は多く存在します。
話すのが苦手だからといって、自分を責めたり、「明るく元気にしなきゃ」と無理をする必要はありません。
それよりも、
- 自分が落ち着いて働ける職場はどこか
- 自分のペースが許される空気はどんなものか
- 自分の得意を静かに活かせる業界はどこか
を見つけることが、“コミュ障理系の戦い方”における最大のポイントです。
今の自分のままで、戦える場所は必ずあります。
無理に自分を変えるよりも、“向いている環境”を先に探すことこそ、就活を前に進める鍵になります。
文系の業界研究についてはこちらの記事で解説しています。