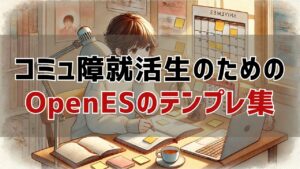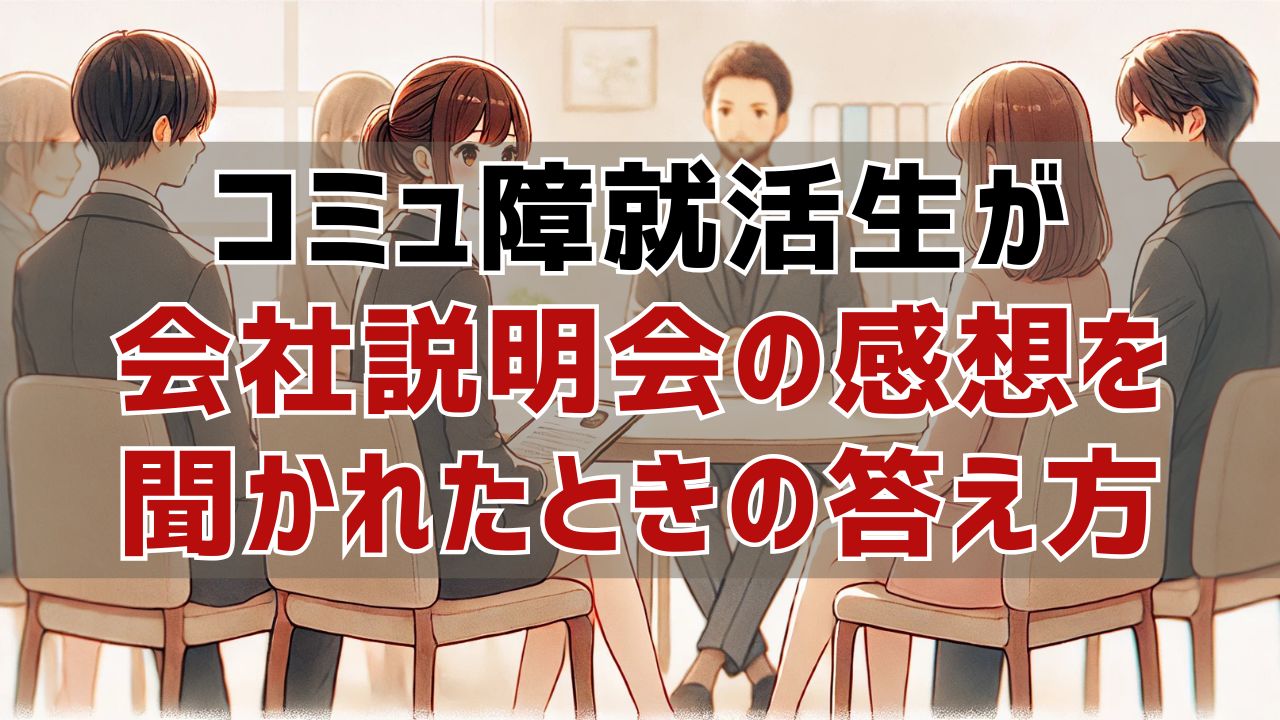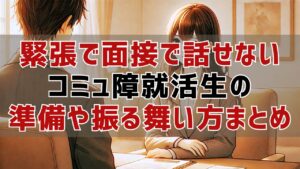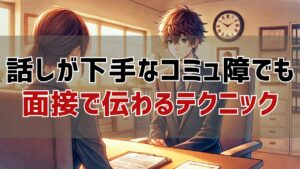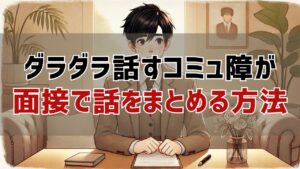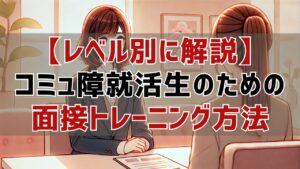「会社説明会の感想を書いてください」と言われて、正直ちょっと身構えてしまう。
「変なことを書いて印象が悪くなったらどうしよう」
「何を書いても浅くなる気がする」
そう感じて、筆が止まる人は少なくありません。
特に、コミュ障気質の人にとっては「言葉で自分を表現する」こと自体が大きなハードル。
そのうえで、説明会の感想には“何か気の利いたことを書かなきゃいけない”というプレッシャーも感じてしまいがちです。
でも、大丈夫です。
採用担当として学生の感想を何百と読んできた立場から言わせてもらうと、「正直に、丁寧に、自分の目で見たことを書いているか」さえ伝われば、それだけで評価につながることは多々あります。
この記事では、そんな「話すより書く方が安心」な就活生に向けて、会社説明会の感想を怖がらずに書くための方法を、ていねいに解説していきます。
「会社説明会の感想を教えてください」と言われたとき、何を見られてる?
「説明会ってただの情報収集の場じゃないの?」
「感想を書いたら評価されるのかな…」
こんな疑問や不安を抱く就活生は多いと思います。
特に、コミュ障タイプの人ほど「変なこと書いたらどうしよう」と身構えてしまうかもしれません。
結論から言えば、会社説明会そのものが“直接的な選考の場”になることは少ないです。
ですが、感想の内容や態度から“印象”を持たれることはあるので、完全に油断していい場ではないとも言えます。
企業が感想を求める理由は、主に以下の3つです。
理由①:どこに関心を持ってくれたのか知りたい
企業側は、「どの部分が学生に響いたか」を知ることで、自社のアピールが届いているかを確認したいと考えています。
たとえば、
「○○という制度に興味を持ちました」
「△△という取り組みが意外で印象に残りました」
など、具体的な反応があると、企業側も「ちゃんと聞いてくれていた」と感じるものです。
理由②:志望度の“目安”として見ている場合も
説明会で何を感じたかは、その企業にどれだけ興味を持っているかの“間接的な証拠”になります。
「業務内容が理解できた」
「福利厚生に安心した」
「若手の活躍に魅力を感じた」
などのコメントがあれば、「この学生は真剣に聞いていた」「志望度が高そう」とポジティブに受け止めてもらえることもあります。
もちろん、どれも当たり障りのない内容でもマイナスになるわけではありませんが、“無記入”や“適当な言い回し”だと印象が残らないのも事実です。
とくに採用人数が少ない企業では、感想文から学生の志望度をなんとなく見極めていることもあります。
とはいえ、「うまく書けなかったから落ちる」といった直接的な影響があるわけではありません。
あくまで、「今後の選考に進む可能性が高いかどうか」の判断材料のひとつとして見られている程度です。
理由③:今後の説明会運営のヒントにしたい
感想はフィードバックとしても貴重です。
「もっと○○について詳しく聞きたかった」
「社員の方がフランクで話しやすかった」
こういった意見は、企業にとっても次の説明会をよりよくするためのヒントになります。
補足:「評価しない」と言いつつ“人柄チェック”の材料になることも
企業は「説明会の感想で評価はしません」と明言することもありますが、実際には“どんな受け答えをする人か”の参考にされることもあります。
たとえば、基本的なことですが、
- 丁寧な言葉で書かれているか
- 何かひとつでも拾って書こうとしているか
- 否定的でも礼儀を保っているか
といった要素から、「この学生は誠実そう」「相手に敬意を持てる人だ」といった印象を持たれることもあります。
感想は、“評価の対象ではないけれど、印象には残るもの”だと考えておくのが現実的です。
コミュ障就活生のための感想を書くときの3つの基本ポイント
「どこが印象に残ったかと言われても、気の利いた感想なんて書けない….」
そんな不安を抱えているコミュ障就活生のために、感想を“考える”のではなく“組み立てる”ためのテンプレートを紹介します。
実際、感想は“上手さ”よりも“丁寧さ”が大切。
文章力に自信がなくても、以下の3ステップに沿って書くだけで、印象に残る感想が作れます。
ステップ①:印象に残った内容を1つ選ぶ
最初にするのは、「あ、これはちょっと覚えてるな」と思える内容を1つ決めること。
- 若手社員が主体的に働いている話が印象的だった
- 女性の働きやすさを制度で支えていると知って驚いた
- 社員の方が楽しそうに働いていたのが印象に残った
「覚えている=自分の感情が動いた証拠」なので、そこに注目してみてください。
ステップ②:なぜそう感じたかを短く書く
次に、その内容がなぜ心に残ったのかを一言添えます。
ここは、理屈よりも“自分のリアクション”を書くほうが自然です。
- 自分も早いうちから仕事を任されたいと思っていたので、魅力に感じました
- 働き方に不安があったので、安心感につながりました
- その場の雰囲気が明るく、リアルにイメージできました
「○○だったから印象に残った」とシンプルにつなげばOKです。
ステップ③:自分との接点・価値観を少し添える
最後に、自分の価値観や性格と関連づけられると、より説得力が増します。
- 「人と協力して働く環境が合っていると感じたので、自分に向いていると感じました」
- 「静かな性格なので、社内の落ち着いた雰囲気に安心しました」
- 「福利厚生の充実度に共感し、長く働ける環境を求めている自分に合っていると思いました」
テンプレートまとめ
以下の形でまとめれば、感想として十分通用します。
○○という話が印象に残りました。
□□だと感じたからです。
私自身、△△を大切にしているため、より一層興味が湧きました。
このテンプレートを使うと、たとえば、
若手社員が自分のアイデアを発信できる環境があると聞き、印象に残りました。
早くから挑戦できる社風に魅力を感じたからです。
私自身も、新しいことを考えるのが好きなので、自分の意欲が活かせると感じました。
というように無難な感想が完成します。
よくある設問と“答え方のコツ”
会社説明会の感想でよく聞かれる設問は、だいたいパターンが決まっています。
ただし、どんなにテンプレっぽい質問でも、答え方に“ちょっとした工夫”を加えるだけで、印象は大きく変わります。
ここでは、コミュ障でも無理なく答えやすくなるように、具体例を交えてコツを解説します。
Q1. なぜ説明会に参加しようと思ったのか
- 「理由+ちょっとした期待」のセットにすると自然。
- 志望度が高くなくても、“情報収集”のスタンスで書けばOK。
Q2. どこで当社を知ったのか
- 情報源+気になった理由、まで書くと印象がよくなる。
- 「一言で終わらせない」だけで丁寧さが伝わる。
Q3. 良かった点と改善点を教えてください
- 良かった点は素直に書く。
- 改善点は“個人的に感じたこと”として表現するとやわらかい。
Q4. 印象に残ったことを教えてください
- ひとつだけに絞ってOK。
- 「なぜ印象に残ったか」まで書けると深みが出る。
Q5. 印象はどう変わりましたか?
- 「予想」と「実際」のギャップを書くと説得力アップ。
- 変化が小さくても、具体的に描写すると印象に残る。
Q6. 今後の選考を希望しますか?
- 本音が未定でも、“興味を持っている”ことは素直に書く。
- 「理由」まで添えると、前向きさが伝わる。
関連記事
感想やESで「どうしても浅い話になってしまう…」という方には、伝え方に深みを持たせるための構成術も紹介しています。
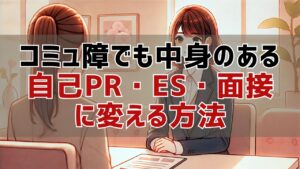
コミュ障就活生が気をつけたい感想のNG例と言い換え
説明会の感想を書くとき、つい使ってしまいがちな“NG表現”があります。
どれも悪気はないのですが、企業側から見ると「なんとなく印象が薄い」「受け身な印象がある」と受け取られてしまうことも。
特にコミュ障タイプの人は、“失礼にならないように”と無難な表現を選びすぎて、逆に印象がぼやけてしまうことがあります。
ここでは、やってしまいがちなNG表現と、その言い換え方を具体的に紹介します。
NG①:「特にありません」
「覚えていない」「興味が持てなかった」と思われてしまう典型的な返答。
完璧な感想が書けなくても、何か1つ拾って言葉にすればOKです。
○○の取り組みを初めて知ったので、印象に残りました。
まだ理解しきれていませんが、もっと詳しく知りたいと思いました。
NG②:「全部よかったです」
前向きな言葉に見えても、具体性がないため印象には残りにくい返答です。
どこが良かったのかを1つに絞って伝えた方が、誠実さが伝わります。
特に○○の説明が分かりやすく、事業内容への理解が深まりました。
自分が働くイメージも少しできた気がします。
NG③:「他社より良かったです」
比較は一見ポジティブに見えても、「他社を下げて自社を持ち上げている」ように聞こえてしまうためNGです。
大切なのは、自分が感じた“共感”や“価値観との一致”を伝えることです。
○○の制度を聞いて、安心して働けそうだと感じました。自分に合った働き方ができる会社だと思いました。
NG④:「なんとなく印象に残りました」
“なんとなく”という表現は、曖昧さが強く、感想としては弱い印象を与えがち。
「なぜそう感じたか」を一言でも添えることで、説得力が出ます。
若手社員の方が仕事について率直に話してくださったのが印象的でした。自分の将来像を少し想像できて、親近感を持ちました。
NG⑤:「普通でした」「特に印象は変わりませんでした」
“ネガティブではない”つもりでも、「無関心そう」に受け取られる危険性があります。
ポジティブな気づきをひとつ拾って、「少しでも変化があった」ことを示せるとベスト。
思っていたよりも社内の雰囲気が柔らかく、社員の方の話を聞いて働きやすそうだと感じました。
こうした表現は、ほんの少しの言い換えで印象がガラッと変わります。
「話すのが苦手」だからこそ、“言葉の選び方”で評価されるチャンスもあるのです。
関連記事
あらかじめ企業研究をしておいた方が感想も書きやすいかもしれません。
「どういう部分に注目すればいいかわからない」という方は、企業研究のポイントをまとめたこちらの記事も参考になります。

書くときに気をつけたい3つのポイント
会社説明会の感想は、“ただのアンケート”ではなく、企業にあなたの人柄や姿勢が伝わる機会です。
特にコミュ障の人にとっては、「うまく書けない」「どう思われるか不安」と感じやすい部分ですが、ほんの少しの工夫でグッと伝わる感想になります。
ここでは、感想を書く際に意識したい3つの基本ポイントを紹介します。
ポイント①:箇条書きではなく、短くても文章形式で書く
たとえば、次のような書き方はNGです。
- 社員の雰囲気が良かった
- 話がわかりやすかった
箇条書きだと「丁寧に書いていない」「考えが浅い」と見られることも。
社員の方の話し方が柔らかく、働く環境も穏やかそうだと感じました。
説明も丁寧で、入社後のイメージが少し持てました。
短くても文章にすることで、「ちゃんと考えて書いているな」という印象になります。
ポイント②:誤字脱字をチェック。社名・人名は特に注意!
緊張していても、企業名や社員の名前にミスがあると「興味がないのかな?」と思われてしまう可能性があります。
書く前には、必ず社名の正式表記を確認し、書いた後には声に出して読み直してみましょう。
たとえば、「株式会社〇〇」 を 「○○(株)」などと略すのは避けるのがいいですね。
文章内容より、こうした“基本的なマナー”が印象を左右することもあります。
ポイント③:難しい言葉より、自分の言葉で書いた方が伝わる
「しっかりした感想を書かなきゃ」と思うあまり、ネットで拾った言葉や“正解っぽい”表現を使いたくなることもあるかもしれません。
でも、企業側が見ているのは“文章のうまさ”ではなく、“その人の目線”や“感じたこと”。
だからこそ、「〜と思いました」「〜と感じました」でOK。
社員の方が笑顔で話していて、会社の雰囲気が良さそうだなと思いました。
こうした素直な言葉のほうが、むしろ信頼感を与えます。
感想を書くときは、「上手に書く」より「その人らしさが出ている」かどうかが大事です。
まとめ:感想が書ければ“無言の評価”は跳ね返せる
面接ではうまく話せなくても、会社説明会の感想では「自分のペースで、自分の言葉で伝える」ことができます。
そしてそれは、あなたが話せなくても真剣に向き合っていることを伝える、数少ない“書けるチャンス”でもあるのです。
むしろ、感想という場面では
- ていねいに感じたことを拾える
- 一言を慎重に選ぶ
- “ちゃんと読んで考えた”ことがにじみ出る
といった、静かめタイプの就活生の強みが活きます。
感想文は「自分の感じたことを、自分の言葉で伝える」だけでいい。
その姿勢が、見ている人にはちゃんと伝わります。
あなたのその一言が、採用担当者にとっての“安心材料”になることもあるのです。
もし、感想だけでなく、ES(エントリーシート)でも書くことに不安がある方は、“テンプレートと例文”で書けるようになるこちらも参考にしてください。