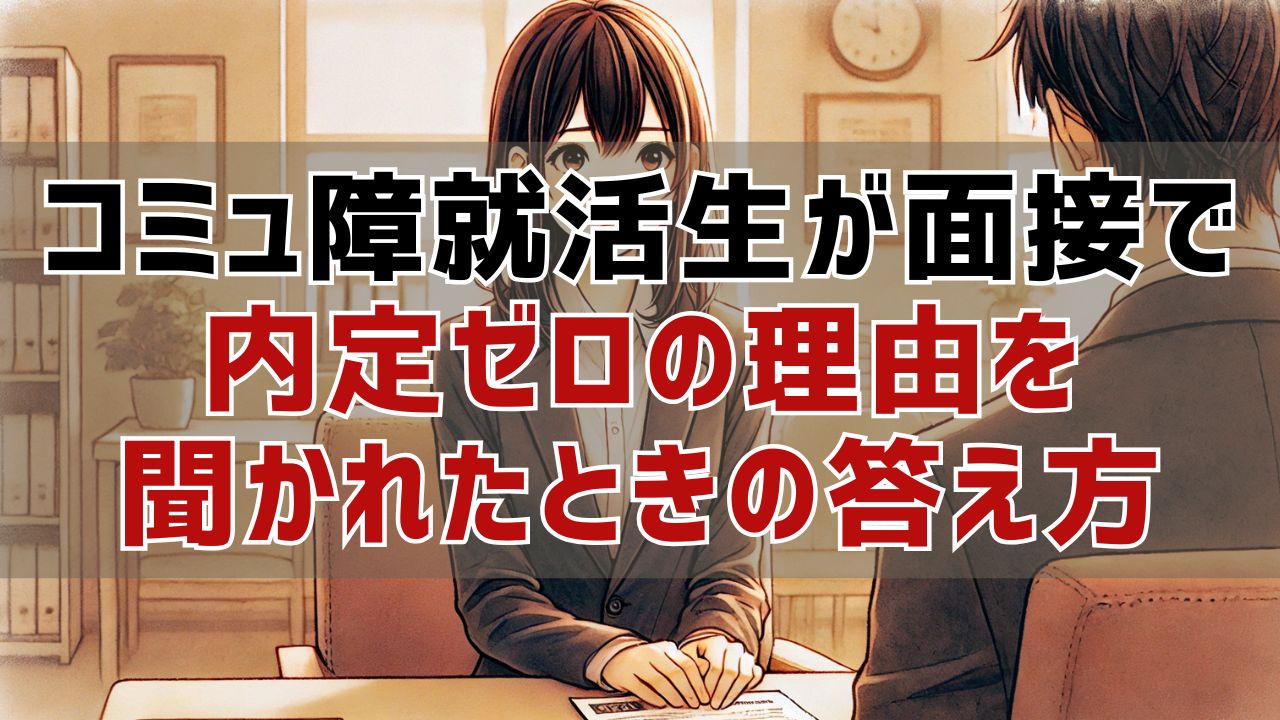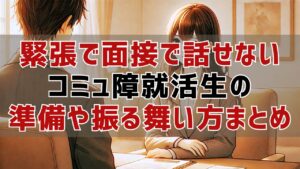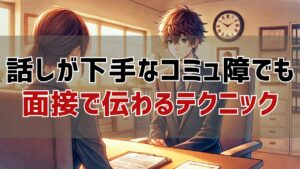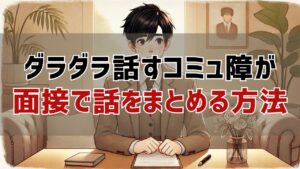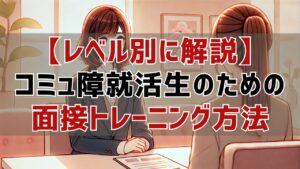就活が夏・秋に差し掛かると、「内定が出ていない理由をどう説明するか」に悩む人が増えてきます。
特に、話すことが苦手なコミュ障就活生にとっては、ただでさえ緊張する面接の中でこの質問をされるのは、プレッシャーが大きいものです。
ただ、面接官として採用側に回った経験もある今振り返ると、「内定がないこと」そのものを責めている企業はほとんどありません。
むしろ、「その状況をどう受け止めていて、どう行動しているか」が見られています。
そこで今回は、コミュ障就活生が「内定がない理由」を面接で聞かれたときに、ネガティブにならずに伝えるコツや、具体的な回答例を紹介していきます。
- 面接で「内定がない理由」を聞かれる背景と意図
- コミュ障就活生が伝えるべき4つのポイント
- 面接官に納得感を与える回答テンプレートと例文
- 言ってはいけないNG回答の避け方
関連記事
面接で結果が出ない状態が続いている方は、「全滅状態から逆転するためのポイント」を解説したこちらもぜひご覧ください。
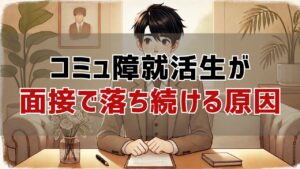
夏・秋採用で「内定がない理由」を聞かれやすいのはなぜ?
6月以降、就活は「後半戦」に入ります。多くの企業では春の採用活動が一段落し、面接官も「そろそろ内定を持っている学生が多いだろう」と考えながら面接に臨むようになります。
そのため、内定がまだ出ていない学生に対しては「なぜまだ決まっていないのか?」を自然と確認したくなるのです。
決して責める意図ではなく、そこには明確な“評価の視点”があります。
面接官が「内定がない理由」を聞くのはコミュ障っぽいから?
コミュ障就活生にとって、「内定がない理由を聞かれる」こと自体がかなりプレッシャーになるかもしれません。
でも元面接官としてお伝えしたいのは、「この子はコミュ障っぽいから、なぜ内定がないのか突っ込んでやろう」という意図はまったくありません。
むしろ、どんな考え方で就活に向き合ってきたのか、壁にぶつかったときにどう受け止めて動いたかという、「その人のスタンス」や「今の姿勢」を知るための質問です。
質問の意図①:志望度を確かめたい
企業側からすると、「この時期にウチを選んで受けに来てくれたのは嬉しい、でも…第一志望なのか、滑り止めなのかは気になる」といった本音があります。
たとえば、以前私が面接官をしていたとき、ある学生が「これまで色んな業界を見てきたんですが、やっぱり御社のような安定感のある企業が合っていると思って…」と話していました。
このとき、「それって他がダメだったから選んだのでは?」という不安がよぎりました。
その学生は悪気なく話していたと思いますが、「今のタイミングでこの企業を志望している理由」をきちんと話せるかどうかで、印象が大きく変わる場面です。
質問の意図②:「ちゃんと準備してる人か」を判断したい
春から何社も面接を経験しているはずなのに、話し方がずっとたどたどしかったり、志望動機が浅いと、「今まで何をしてきたの?」と思われてしまいます。
逆に、過去にうまくいかなかった理由を自分で分析し、「そのために今はこういう準備をしている」と話せる学生は、グッと信頼度が増します。
実際、私自身がコミュ障就活生だった頃、6月時点で内定ゼロでした。
面接で「まだ決まってない理由は何ですか?」と聞かれ、最初は焦って曖昧に答えてしまったことがあります。
でも、あるとき「話す順番を決めていなかったので、言いたいことがまとまらなかった」と正直に伝えました。
そして、「そこから話す順番を紙に書き出す練習をした」と話したところ、面接官の反応が一気に変わった経験があります。
質問の意図③:「責任転嫁しない人か」を見ている
「内定がない」という状況は、誰にとってもつらいものです。
でも、ここで「企業側と合わなかった」「たまたま倍率が高かった」と他責の姿勢が見えると、それだけでマイナス評価になってしまいます。
私が採用担当をしていた頃も、「選考が不公平だった気がして…」といった発言をする学生には正直、違和感を持ってしまいました。
逆に、「最初は緊張しすぎて話せなかったけど、最近は答えの“最初の1文だけ”を決めてから臨むようにしています」と自分の行動で変化を見せてくれる学生は、応援したくなりました。
質問の意図④:落ち込んだ経験への向き合い方を見ている
面接官は、成功体験だけを聞きたいわけではありません。
むしろ、「うまくいかなかった経験」をどんな風に受け止め、どう立て直してきたのかのほうが、よく見ています。
私自身、元コミュ障就活生だった頃、「言葉に詰まって泣きそうになった面接」がありました。
でも、そこで終わりにせず、「何が足りなかったか」「どう準備すればもう一度話せるか」を考え、自己紹介の一言目だけを練習するようにしました。
結果的にその対策が次の面接で活き、内定につながった経験があります。
質問意図⑤:企業との相性や“自分軸”の有無を確認している
「内定がない=能力が足りない」ではなく、単純に合う企業に出会えていないだけというケースもあります。
だからこそ、面接官は「どんな企業を受けてきたのか」「何を軸に選んでいるのか」を知りたがります。
このとき、話がフワッとしていると「そもそも何を基準に企業を見てるのか分からないな…」と思われてしまいます。
逆に、「人間関係の穏やかさを重視していたのに、テンション高めの会社ばかり受けてしまっていた」など、軸と現実のズレに自分で気づいていれば、それはむしろ評価されるポイントになります。
夏・秋の面接では、「なぜまだ決まっていないのか」を聞かれる確率は高くなります。
でも、それはダメ出しではなく「今のあなたを知る質問」です。
焦らず、「過去の自分」「そこからの気づき」「今の取り組み」をセットで話せる準備をしておきましょう。
コミュ障就活生が「内定がない理由」の答え方で伝えるべき4つのポイント
内定が出ていない理由を答えるときに一番大切なのは、「落ちたこと」ではなく「どう向き合ってきたか」を伝えることです。
元面接官の立場から言うと、ここに“自責で整理できているか”“改善の跡があるか”が見えるかどうかで、印象がまったく変わります。
ポイント①:原因は“自責で整理”し、他責は避ける
「面接官との相性が悪かった」「どこも倍率が高すぎた」など、つい言いたくなる気持ちは分かります。
でも、採用する側からすると「人のせいにする人」として映ってしまい、評価は下がってしまいます。
たとえば私は就活中、「説明が長くて何が言いたいのか分かりづらい」と面接後に指摘されたことがありました。
そのときに、「質問が難しかった」と思うのではなく、「結論から話す練習が足りなかった」と受け止め直したことで、次の面接で話の構成を大きく改善できました。
ポイント②:反省だけで終わらず、改善策を必ず入れる
「うまくいかなかったです」「話せませんでした」で終わってしまうと、「今も変わっていないのかな?」と不安に思われがちです。
たとえば、「最初は志望動機をうまく言えず、浅い内容で終わってしまったのですが、今は“企業の取り組みと自分の経験をセットで話す”練習をしています」のように、改善の過程を伝えると納得感が増します。
ポイント③:気づいたこと・行動の変化を具体的に話す
反省しただけでなく、「だからこう変えた」と話すと、相手は“成長できる人”という視点で見てくれます。
私が面接官をしていた頃、「自己PRで失敗した経験がありますが、録音して聞き直すことで、声のトーンや話の速さを調整しました」と言った学生がいました。
実際にその場でも落ち着いて話していて、行動の裏付けが感じられ、印象に残りました。
ポイント④:「だから今はこうしている」と未来志向で締める
たとえ苦戦していても、“今どう取り組んでいるか”を明るく語れる人は強いです。
過去の失敗はどうでもよくなるくらい、“今”の姿勢が評価されます。
たとえばこんな感じです。
話すのが苦手で、最初の面接はほとんど何も伝えられませんでした。
ただ、録音で振り返るようになってから少しずつ改善し、今は“結論から話す型”で安定してきたと感じています。
今日も、その練習を意識して臨んでいます。
こうした話し方ができれば、「成長している最中なんだな」とプラスに受け取ってもらえます。
【コミュ障就活生向け】「内定がない理由」の答え方テンプレート
「内定がない理由」を面接で聞かれたとき、コミュ障の就活生ほど構えてしまいがちです。
でも実際は、“失敗そのもの”よりも「どう受け止め、今どう動いているか」のほうが重視されます。
ここでは、コミュ障として就活に苦戦した経験のある立場から、使いやすい3つのパターンと、その意図を解説します。
例文①:話すのが苦手で、最初は自信を持てなかった
初期は面接に強い不安があり、自信のなさから言いたいことがうまく言えませんでした。
ですが、話し方の“型”を取り入れて練習することで、少しずつ落ち着いて話せるようになってきました。
最近は、“相手に伝えること”を意識して面接に臨めるようになっています。
「苦手でした」だけではマイナスですが、「練習したこと」「改善してきたこと」が明確になっているので、誠実に努力できる人と評価されやすくなります。
とくに“今どうなっているか”がポジティブに語られている点が大事です。
例文②:準備の方向性がズレていて、志望理由が浅かった
春頃は、準備の仕方が表面的で、志望理由も企業ごとの理解が浅かったと思います。
選考後に企業研究の重要性に気づき、今は1社ずつ“働くイメージ”を持って話すようにしています。
その分、面接でも自然に言葉が出てくるようになってきました。
「何がズレていたのか」「どうして気づいたのか」「今どう変えたのか」の流れが自然で、成長の過程がしっかり伝わる回答です。
「失敗→学び→行動」の構造があると、面接官としても安心できます。
関連記事
志望理由が浅くなると感じた方は、企業研究を通じて“自分との接点”を見つける戦略が効果的です。
企業研究のやり方と面接への活かし方はこちらの記事でまとめています。

例文③:緊張でうまく話せなかったが、今は型を使って安定してきた
元々、面接では緊張しやすく、うまく話せずに終わることが多くありました。
でも、“結論→理由→エピソード”の話し方を練習し、話す順序を決めておくことで、少しずつ安定感が出てきました。
面接を重ねる中で、失敗を振り返って改善する癖もつき、今は落ち着いて話せるようになってきています。
“緊張する人”は多いので、それをどう乗り越えてきたかがポイントになります。
「緊張しても話し切れる人」「改善できる人」と思ってもらえれば、十分に逆転可能です。
コミュ障就活生が「内定がない理由」の回答時に気をつけたい3つの注意点
「誠実に話したのに、なぜかマイナス印象だった…」というのは、面接に不慣れなコミュ障就活生に多いケースです。
理由の多くは、“内容”ではなく“伝え方”にあります。ここでは、元面接官の視点から、ありがちな失敗パターンとその対処法を解説します。
NG①:愚痴・言い訳・運のせいにしない
- 面接官の質問が合わなかった
- たまたま相性が悪かった
- 緊張して本来の自分が出せなかった
これらの表現は、言いたくなる気持ちは分かります。
ですが、面接官側からすると「この人は失敗を人のせいにするタイプかも」と受け取られてしまいます。
もし「緊張していた」と言いたいときは、「緊張する場面でも話せるように〜という対策をした」と“行動ベース”で話すのがおすすめです。
NG②:反省モードになりすぎて暗くなる
- うまくいかない自分が嫌になって…
- 正直、自己嫌悪になってしまいました
これも素直で正直な気持ちだと思います。
ただ、面接の場で“落ち込んでいる雰囲気”を出しすぎると、「この先もうまくいかないときに立て直せるのか?」という不安材料になります。
もちろん「落ち込んだ経験があった」ことはOKです。
しかし、そのあと「でも、○○をきっかけに気持ちが切り替わった」という流れにして、“回復力”を見せるようにしましょう。
NG③:「だから御社に入りたい」の無理なつなぎ方を避ける
内定が出なかったのは御社と出会っていなかったからです
一見ポジティブなようですが、面接官からすると「ごまかしてるな」「こじつけっぽい」と感じられてしまいます。
ですので、
- これまでの失敗から、こういう軸が自分に合うと気づいた
- だから御社に魅力を感じた
という「気づき」から「選んだ理由」の流れにすれば、納得感が出せます。
まとめ:「内定がない=失敗」ではない。大事なのは“今どう動いているか”
改めて、元コミュ障就活生としての経験、そして元面接官としての立場から強く伝えたいことは、
内定が出ていないことはその人の価値とは関係ない
ということです。
実際、私は採用担当として多くの学生を見てきましたが、「夏以降にグンと成長して、最終的に内定を複数得た人」は少なくありませんでした。
特に、コミュ障タイプの方は準備に時間がかかる分、秋・冬にようやく自分のペースで戦えるようになることが多いです。
だからこそ、
- 過去の失敗をどう受け止めたか
- そこから何を学んで、どう動いているか
- それをどう未来につなげているか
この3つがしっかり伝われば、面接官の評価は十分に変えられます。
もし、今あなたが「内定ゼロ」で悩んでいたとしても、それは通過点にすぎません。
焦るよりも、「今の自分にできる改善」をひとつずつ積み重ねていきましょう。
それが、あなたらしい形での“逆転”につながっていきます。
もし「夏が過ぎても内定ゼロ…」という方は、秋・冬からの巻き返し戦略と準備の進め方をまとめたこちらの記事もご覧ください。