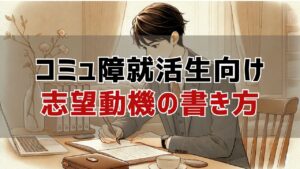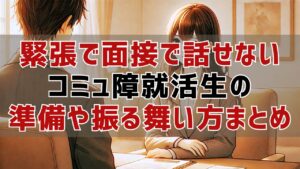“元コミュ障就活生”が、今は就活サポーター

はじめまして。当サイトを運営しているハヤト(33歳・元民間企業の採用担当)です。
コミュ障すぎて
「自己PRが書けない…」
「面接で沈黙してしまう…」
「辛い就活から逃げ出したい…」
そんな就活の悩みを抱えている、かつての自分のような人に向けて、このサイトを立ち上げました。
大学時代は、人と話すのがとにかく苦手でした
大学時代の私は、人前で話すことが本当に苦手でした。
いわゆるコミュ障でした。
教育学部に所属していたので、将来は教員になることも考えていたのですが…。
模擬授業のたびに緊張で声が震え、頭が真っ白になってしまう自分に、だんだん自信を失っていきました。
「こんなコミュ障な自分が、教壇に立って生徒の前で話せるわけがない」
そう感じたとき、心のどこかで教員の道をあきらめていたのだと思います。
ただ、じゃあ民間企業で働けるのか?と言われると、それも不安でした。
サークルやゼミでは、発言のタイミングを掴めず黙ってばかり。
雑談もうまくできず、「話すのが得意な人」ばかりが活躍しているように見えて、自分には社会に出る力がないんじゃないか。
そんなふうに自己否定をする毎日。
当然、就活も怖かったです。
でも、3年生のある日、周りの友人たちを見ると動き出していたのです。
教員採用試験の勉強、インターン、自己分析。
「このまま何もしないで卒業したら、本当に後悔する」と私は感じました。
そう思って手に取った就活本には、
「自己PR」「学生時代に力を入れたこと」「志望動機」
と、聞いただけで固まりそうなワードがずらりと並んでいて、完全にフリーズしました。
それでも、逃げたままでは変われない。
そう思い直して、少しずつ就活と向き合い始めたのが、私のスタートラインでした。
それでも就活を乗り越え、大手企業に就職
人と話すのが苦手な私にとって、就活は正直いうと修行のような日々でした。
初めての面接では、緊張しすぎて頭が真っ白になり、何を聞かれたのかさえ思い出せないほど。
「……えっと、すみません、忘れました」としか答えられず、面接官の表情が曇っていくのが分かって、余計に焦ってしまいました。
当然、不合格。
駅までの帰り道、情けなさと悔しさで涙が出てきて、「やっぱり自分には無理なんじゃないか」と思いながらうつむいて帰りました。
その日の夜、何をする気にもなれず、スマホで「面接 うまく話せない」と検索していたときのこと。
何気なく開いたある就活記事に、こう書かれていたんです。
「話すのが苦手な人でも、“準備”と“伝え方”で就活は乗り越えられる」
最初は半信半疑でした。
でも、その記事には、「話すのが苦手なら、無理にうまく話そうとしなくていい。順番や型を決めて、伝わりやすくする工夫をすればいい」と、私にもできそうな工夫がいくつも紹介されていました。
「あ、自分だけじゃなかったんだ」
「こんなふうに考えていいんだ」
その瞬間、心のどこかでふっと力が抜けたというか、初めて就活に希望のようなものを感じたのを覚えています。
それからは、少しずつ「自分に合った就活」を模索しはじめました。
- 話すのが得意じゃないなら、伝える順番を決めておこう
- 緊張するなら、想定質問と答えを何度も練習しよう
- 詰まっても慌てないように、「ごめんなさい、少しだけ考えさせてください」と言う練習もしておこう
完璧じゃなくてもいい。
ただ、自分にできる準備を、丁寧に積み重ねることだけを意識しました。
すると、少しずつですが言葉が自分の中に馴染んでいき、エントリーシートも「自分の言葉」で書けるようになっていきました。
そして何社もの不合格を経て、ようやくひとつ、内定をいただくことができました。
それは、周りから見れば特別な企業ではなかったかもしれません。
でも私にとっては、「話せない自分でも前に進めた」ことを証明できた、かけがえのない内定でした。
採用担当として、何百人もの就活生を見てきました
23歳で入社後、人事部に配属され、最初は新人研修や総務系の業務を担当していました。
その後、3年目から新卒採用に本格的に関わるようになり、トータルで約4年間、新卒採用担当として活動しました。
「面接官として学生を見るなんて、自分にできるのか?」と最初は不安でしたが、いざやってみると、過去の自分の経験がものすごく活きることに気づいたんです。
- 面接で緊張して言葉に詰まってしまう学生
- うまく話せない自分に自信を失っている学生
- 書いているESの内容に説得力がなく、何を伝えたいのか迷っている学生
見れば見るほど、かつての自分とそっくりな学生たち。
だからこそ、私は「どうすれば彼らの良さを引き出せるか」を常に考えて面接していました。
そして気づいたのは、「話し上手=評価される人ではない」ということ。
- 伝え方を工夫している人
- 言葉に詰まりながらも、誠実に向き合っている人
- 話すのが苦手でも、自分の強みを一生懸命届けようとする人
こういう人こそ、「この子と一緒に働きたい」と思わせる力を持っていると知りました。
過去の自分と同じように悩む人の力になりたい
私は今、フリーランスとして働きながら、この「コミュ障でも就活できるサイト」を運営しています。
きっかけは、ある後輩のひと言でした。
ハヤトさん、昔めちゃくちゃ面接苦手だったって言ってましたよね?
でも今、人事やってたってことは、何かコツがあるんじゃないですか?
それ、まとめてネットに出してくれたら、絶対助かる人いますよ
その言葉に背中を押され、「かつてのコミュ障の自分に読ませたい就活ノウハウ」を、今こうして発信しています。
このサイトで伝えたいのは、ただの情報やテクニックではありません。
「話すのが苦手でも、伝わる手段はある」という希望です。
「コミュ障だからこそできる就活戦略」を伝えたい
このサイトは、「コミュ障」という言葉で自分を否定しなくていい就活のやり方を発信することをコンセプトにしています。
よくある就活サイトでは、「はきはき話そう」「表情を明るく」「堂々とした自己PRを」など、“理想的な就活生像”を前提にしたアドバイスが並んでいます。
でも、それができなくて悩んでいる人にとっては、「結局、自分には無理なんだ…」と、逆に自信を失うことも多いはずです。
私自身がそうでした。
だからこのサイトでは、“できない”ことを前提にした戦略を提案しています。
たとえば、こんなテーマを扱っています
- 声が小さい人が好印象を残すための「話し方」ではなく「伝え方」の工夫
- 雑談が苦手でも面接で好感を持たれる「準備と型」の使い方
- 自己PRが浅いと思われないための「切り口の変え方」
- 表情が硬い人が「無理に笑わず」印象を良くする方法
- 面接で詰まったときの「リカバリー用フレーズ」や「緊張対策」
- 「話せない前提」で設計するグループディスカッション戦略
どれも、「話すのが得意じゃない人」「堂々と振る舞うのが苦手な人」が、“自分の特性を無理に変えなくても戦える方法”を軸にしています。
採用担当としての知見 × 自分自身の実体験
このサイトのもう一つの特徴は、
「面接で見られているポイント」
「ESで評価される要素」
など、実際に私が採用担当として見てきた側の視点を組み合わせていることです。
表面的な就活テクニックではなく、「なぜこの表現が伝わるのか」「なぜこの対策が有効なのか」といった理由や背景も含めて丁寧に解説しています。
さらに、ただのアドバイスにとどまりません。
“かつての自分だったらこう使った”という視点も加えて、読んでくれた人が「これならできそう」と思えるよう、等身大のアドバイスを心がけています。
誰かの“就活の味方”になるサイトを目指して
このサイトは、「誰かの就活を劇的に変える」ような派手さはないかもしれません。
でも、「一人じゃないと思える」「少し前に進めそう」と感じてもらえることを、何よりも大事にしています。
コミュ障だった私だからこそ書ける、リアルな言葉と実践的なノウハウ。
それを必要としてくれる人に、まっすぐ届けていきたいと思っています。
最後に 〜誰よりも「怖さ」を知っているから、伝えられることがある〜
就活が怖い…。
人と話すのが怖い…。
「落ちたらどうしよう」と毎日ビクビクしている…。
これ、全部、かつての私につきまとっていたものです。
だからこそ私は、今も「自分のような人でも、就活を乗り越えられる」ということを伝えたくて、記事を書き続けています。
あなたが今、どれだけ不安を感じていたとしても、「変われるきっかけ」はきっと見つかります。
このサイトが、そんなきっかけのひとつになれば幸いです。
ぜひ他の記事も、あなたのペースで読んでみてくださいね。
おすすめの記事