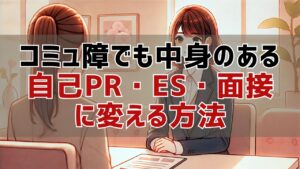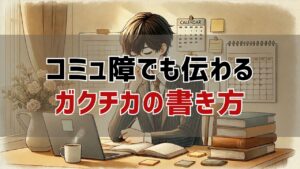「自己PRって、何を書けばいいのか分からない…」
「話すのが苦手だと、アピールもできない気がする…」
そんなふうに悩む就活生の中には、“コミュ障”という言葉で自分を責めてしまっている人も少なくありません。
でも大丈夫。話すのが苦手=アピールできない、ではないんです。
この記事では、私の実体験をもとに、
- コミュ障でも通用する自己PRの考え方
- 評価されやすい構成の作り方
- “話せない”を強みに変える表現テク
を、やさしく・具体的にお伝えします。
「話すのは苦手だけど、伝えたい気持ちはある」
そんなあなたが、“自分らしさ”で勝負できる方法を、一緒に見つけていきましょう。
そもそも「自分の強みが見つからない…」という方は、こちらで“自己分析のコツ”から始めてみるのがおすすめです。

話せない=アピールできない、は思い込みです
「自己PRって、面接で堂々と話せる人しか通らないんじゃないの?」
そう思っていませんか?
でも実際は、“話す力”がすべてではありません。
就活は、“伝える工夫”ができる人が評価される場でもあります。
自己PRが書けないコミュ障のよくある思考パターン
コミュ障の人が自己PRに苦手意識を持つ理由は、こんなものが多いです。
- 目立った実績がないから書けない
- 自信がないから、強みと言い切れない
- 面接でうまく話せる気がしないから、そもそも意味あるの?と感じる
私も最初は「堂々とプレゼンできる人じゃないと無理」と思い込んでいました。
でもそれって、「話せる人」前提の就活を見すぎていただけだったんです。
就活は「話す力」だけで決まるわけじゃない
もちろん、話す力も評価ポイントのひとつです。
でも、それは“話せる内容がある”という土台があるからこそ伝わるんです。
逆に言えば、
- 構成がしっかりしている
- 納得感がある
- 自分の特性が整理されている
この3つが揃っていれば、多少話し方がたどたどしくても評価されることはよくあります。
だからこそ、自己PRにおいても「話せない=詰んでる」ではなく、“どう伝えるかを工夫する余地がある”と捉えていくことが大切なんです。
コミュ障向け自己PRの考え方|“話せない”人こそ文章勝負
「面接でうまく話せないから、自己PRなんて意味がない」と感じている方へ。
実は、“話すのが苦手”な人ほど、書類で勝負する戦略が効くという事実があります。
ある就活生のケースを紹介します。
話すのが極端に苦手で、面接では言葉が続かなくなるタイプ。
けれど、その人のエントリーシートには、自分の特性や働き方を丁寧に整理した文章が書かれていました。
採用担当としてその書類を読んだとき、「会って話してみたい」と純粋に思えたのを覚えています。
書類で伝われば、面接でもブレない
自己PRが明確に整理されている人は、面接のときにもブレません。
話すのが得意でなくても、自分の言葉で内容を把握できていると、それだけで安心感があります。
逆に、「とりあえずテンプレを詰め込んだだけ」な文章は、話す段階でぼろが出ます。
これは、現場で何百人と見てきた採用担当の立場からもハッキリ言えます。
だからこそ、話すのが苦手な人ほど、書類での説得力を高めることが鍵になるんです。
“会話の苦手さ”を逆手に取る構成戦略
たとえば、こんな形で構成を考えると、自分の弱みを強みに変換できます。
- 話すのは得意ではないが、聞くことに徹することで相手の本音を引き出すことができる
- 雑談は苦手だが、丁寧な準備や確認作業で信頼を得る力がある
こういった表現は、無理に“自分を盛る”必要がないので、コミュ障の人にも無理なく書けます。
そして読む側にも、「この人は自分をよく理解していて、仕事にどう活かすかも考えている」と伝わります。
つまり、「話せない=ダメ」ではなく、“話せない”からこそ伝わる信頼感や誠実さがあるということ。
それが、コミュ障就活生の大きな武器になります。
また、志望動機も「話せないからこそ、文章で伝える」がカギです。
自己PRと同じように、伝え方の工夫が重要なパートなので、こちらも参考になりますよ。
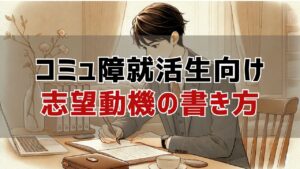
自己PRテンプレ:コミュ障のための3ステップ構成
「何を書けばいいかわからない」
「アピールできるようなエピソードがない」
そんな人でも安心して使える、コミュ障向けの自己PRテンプレをご紹介します。
この構成は、自分の経験を丁寧に振り返りながら、無理のない形で“強み”を言葉にすることができます。
実際に、このテンプレを使って書類選考を通過できた就活生も何人もいました。
ポイントは、“すごさ”よりも“納得感”。
以下のステップを順番に埋めていくことで、あなたらしい自己PRが自然と浮かび上がります。
ステップ①:自分の地味な強みに気づく
コミュ障の人が自己PRでつまずきやすいのが、「特別な強みがない」と思い込んでしまうこと。
でも、強み=すごい経験ではありません。
- 約束を守る
- 丁寧に物事を進める
- 人の話をよく聞く
- 長く続けることができる
こうした一見地味な特性こそ、企業にとっては“信頼できる人材”の証です。
採用の現場では、こうした基本的なことができる人が、実は一番求められています。
ステップ②:強みになった背景やきっかけを思い出す
次に、「なぜその強みを大事にするようになったのか」を考えます。
きっかけは小さなことで構いません。
- 昔、人に気配りができなくて注意された経験
- 集団より1対1の会話の方が安心できたこと
- 急かされるより、じっくり取り組んだときの方が成果が出た経験
背景があると、強みが“自分のもの”として説得力を持つようになります。
ステップ③:強みの根拠となる具体的なエピソードを1つあげる
ここでは、自分の強みが実際に役立ったエピソードを1つ選びます。
小さな話でもかまいません。
例えば、次のようなエピソードでも大丈夫です。
アルバイトでマニュアルをもとに丁寧な引き継ぎメモを作り、後輩から“分かりやすい”と感謝された
学内プロジェクトで、話すより資料作成に力を入れ、全体の進行がスムーズになった
大切なのは、その行動に意味があることを伝えることです。
ステップ④:強みが発揮できた理由や要因をまとめる
エピソードのあとに、「なぜその強みが活かせたのか?」という一言を加えると、深みが出ます。
- 慎重な性格だからこそ、事前の確認を徹底できた
- 自分が話すのが苦手だから、相手が安心して話せるように配慮できた
これによって、“たまたまじゃない強み”として印象に残ります。
ステップ⑤:どう仕事に活かせるかを自然に伝える
最後に、その強みをどう職場で活かしたいかを書きます。
ここでも、大げさに言う必要はありません。
- 裏方の業務で、正確さや丁寧さを求められる場面で力を発揮したい
- 相手の話を聞きながら、気づいたことを言葉にしてサポートしたい
これで、話すのが得意でなくても、一緒に働くイメージが持てる自己PRが完成します。
この5ステップを使えば、「アピールするのが苦手」「何を言えばいいかわからない」という悩みを乗り越えられます。
すぐに書けなくても大丈夫です。
少しずつ自分の言葉にしていきましょう。
自己PRで“コミュ障”を価値に変える表現テク
「コミュ障を強みにするって言っても、どう書けばいいの?」
そんな疑問に応えるために、ここでは“話すのが苦手”という特性をプラスに変える書き方のコツを紹介します。
採用担当として書類を見る中で、「話すのが苦手」とは書かれていなくても、“その人らしい特性”が自然に伝わってくる自己PRは、確実に印象に残ります。
話せないことを隠すのではなく、「だからこそ大事にしていること」を表現するのがポイントです。
「話すのが苦手だからこそ、○○を大事にしてきた」
この型は、コミュ障の特性を前向きに見せるための定番フレーズです。
以下のような言い回しで、説得力のある自己PRになります。
- 話すのが得意ではない分、相手の言葉に丁寧に耳を傾けることを意識してきた
- 雑談は苦手ですが、その分、資料づくりや作業の正確性にはこだわってきた
- 表に出ることは少ないけれど、チームを支える動きにやりがいを感じている
こうした言葉選びは、無理に“明るく振る舞う”必要がない人柄として好感を持たれやすいです。
観察力・継続力・気配りをどうアピールするか
コミュ障の人に多いのが、「目立たないけど地味にすごい力」を持っているタイプです。
特に以下の3つは、企業側が信頼するポイントとして重視している要素です。
観察力
観察力とは、言い換えれば「話す前に周囲を見る力」「相手の様子を感じ取る力」です。
コミュ障の人の中には、「どう話せば変に思われないか」と周りを観察する癖がついている人もいます。
これはビジネスの現場でも重宝されるスキルです。
研究室では後輩の様子を見ながら進捗状況を確認し、無理をしているようであれば先にタスクの調整を提案するようにしていました。
また、プレゼン資料を共同で作成する際も、相手の表情から「この部分の理解が浅そう」と感じたときは、自分から補足説明を入れるようにしていました。
こうしたエピソードを使えば、「空気を読む=受け身」ではなく、“気づきから行動に移せる人”としての観察力を伝えることができます。
継続力
「特別な実績はない」という人でも、“長く続けていること”がある人は非常に評価されやすいです。
企業は、スキルよりも「この人は辞めずに安定して続けてくれそうか」を重視する場面が多いからです。
目立った表彰などはありませんが、学部2年から研究室の日誌記録を継続しており、現在まで2年以上欠かさず担当しています。
細かな機器トラブルや条件の変化をすべて書き留めておくことで、後輩が実験に入る際のマニュアル代わりとしても活用されています。
継続力は、自分を律する力・粘り強く取り組める姿勢の証拠として非常に強いアピール材料になります。
気配り
「人に声をかけるのは苦手だけど、困っている人には自然と動いてしまう」
これは、“言葉ではなく行動で伝える”タイプの優しさや配慮力です。
企業では、表立って話す人よりも、裏で動ける人、地道にサポートできる人が重宝される場面が多くあります。
グループ課題の進行中、メンバーの一人が体調不良で遅れていることに気づいたため、担当部分の進行状況を整理して共有し、追いつきやすいように簡易資料を作って渡しました。
直接声をかけるのは得意ではありませんが、周囲の様子を見ながら“自分ができる範囲でカバーする”ことを大切にしています。
こうした話は、「話さなくても、ちゃんと周りを見て動ける人」という印象につながり、協調性や信頼感のある人物像として評価されます。
“話せない”を“できない”と決めつける必要はありません。
その特性があるからこそ育った力がある。
それを見つけて、言葉にすることで、コミュ障でも評価される自己PRはつくれます。
自己PRはすごくなくていい?不器用でもいい理由は?
「自己PRって、インターン経験とかリーダー経験とか、特別な実績が必要なんじゃ…」
そんなふうに思い込んで、自分には書けないと感じてしまう人も多いはずです。
でも本当に大切なのは、“すごさ”よりも“伝え方”と“積み重ねの中にある人柄”です。
これは、採用の現場で何度も感じてきたことです。
自信がない・ネタがない…そんなときの考え方
たとえば、「話すのが苦手だからグループの中心になったことはない」という人がいたとします。
それでも、「だからこそ周りの人を見ながら静かに支える役割をしていた」と書ければ、それは立派なPRになります。
私が出会ったある就活生は、ずっと裏方の仕事ばかりをしていたそうです。
でも、どうやって全体がうまく動くかを考え、地道に調整していた経験を書いてきました。
例えば、こんなかんじです。
私は、チームの中で周囲を見て静かに支えることを得意としています。
大学のゼミでグループ発表があった際、私は目立つ発表者ではなく、スライドの構成や時間配分、役割分担の調整を担当していました。
複数人で作る資料はどうしてもバラバラになりがちなので、全体の流れがスムーズになるよう、発表順や内容の重なりを整理し、各担当者の進捗に合わせて補助資料を用意するなど、細かい調整を行っていました。
作業中は、メンバーの口数や表情を見て「どこかで困っていそう」と感じたときに、自分から声をかけるのではなく、必要な作業を先回りして進めるよう心がけていました。
最終的に「〇〇さんのおかげで助かった」と言ってもらえたことで、目立つ役割でなくても、自分の関わり方がチームに貢献できると実感しました。
面接ではほとんど緊張で話せなかったのですが、書類の誠実さと整った構成で、「この人と働きたい」と思えたのを覚えています。
“実績”ではなく、“どんな気持ちで行動したか”を伝える。
それが、自己PRの本質です。
「不器用でも信頼される人」に見せる文章の工夫
不器用さを隠そうとするのではなく、「それでも地道にやってきた」姿勢を伝えることで、信頼につながります。
たとえば、
- 話すのが苦手だから、事前にまとめておく習慣がある
- スムーズに進められない分、丁寧さや確認を大切にしている
- 人前でうまく話せないが、1対1のやり取りは大切にしている
こういったエピソードには、派手さはなくても深みがあります。
採用担当としても、「長く一緒に働けそうな人だな」と感じやすいポイントです。
“自己PR=すごい話”という思い込みを手放して、“信頼される人柄がにじむ文章”を目指しましょう。
まとめ:コミュ障でも“伝える力”は育てられる
私も、言葉が詰まるたびに落ち込んで、「こんなんじゃ通るわけない」と思っていた時期がありました。
それでも少しずつ、自分の特性を言葉にする練習を重ねていくうちに、「話せなくても、伝わる自己PR」ができるようになっていきました。
大事なのは、
- 話すのが得意じゃない前提で構成を考えること
- 目立つ実績ではなく、自分らしさを丁寧に表現すること
- 無理をせず、自然体のままで“伝わる言葉”を選ぶこと
この3つさえ意識すれば、コミュ障であることがハンデではなく、「らしさ」として伝わる武器になります。
就活において自己PRは、誰かと比べて勝つためのものではありません。
あなたという人を、あなたのペースで伝えるための手段です。
「話せない自分にも、伝える道はある」
そう信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。
自己PRと同じく、OpenES全体をどう仕上げるかに悩んでいる方はこちらの記事もおすすめです。
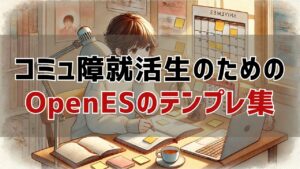
ガクチカのテンプレも紹介しています。