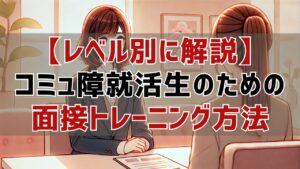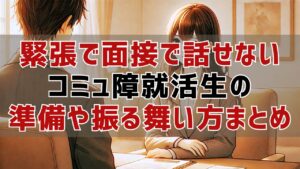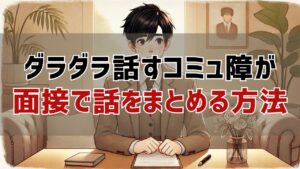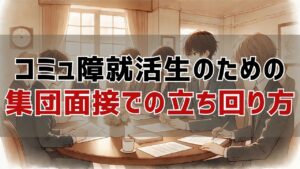「面接で声が震えて、うまく話せなかった」
「どもってしまい、頭が真っ白になった」
声が震えるのが怖くて面接がトラウマになりかけた経験はありませんか?
この記事では、声が震える・どもることに悩むコミュ障就活生のために、
- 面接で声が震える・出なくなる根本的な原因
- 声の震えやどもりを悪化させるNG対応とは?
- コミュ障でもできる毎日3分の“声トレ習慣”
- 面接直前でも効果のある“声の安定ルーティン”
- 緊張しても安心できる話し方のテンプレート
- 声に自信がなくても印象に残る“誠実な話し方”のコツ
日々の練習法から面接直前の対策、安心できる話し方のテンプレまで、実践的な内容を紹介します。
コミュ障就活生が面接になると声が震えて話せない原因は何?
「面接で声が震えるのは、自分のメンタルが弱いから」
そう思い込んでいた時期が、私にもありました。
でも、就活生の声を毎日のように聞いていた面接官としての経験からはっきり言えるのは、声が震えるのは“性格”ではなく、“条件が重なった結果”にすぎないということです。
緊張だけでなく「聞かれている自分」への過敏な反応
緊張していることに加えて、
「自分の話し方がどう思われているか」
「今の声、震えてなかったかな?」
といった“自分への意識”が過剰になると、さらに声が出づらくなってしまいます。
私も就活中、面接中に自分の声の震えに気づいてしまい、「まずい、落ちるかも」とパニックになり、ますます話せなくなった経験があります。
この“自己注目のスパイラル”が、声の震えやどもりをさらに強めてしまうのです。
“慣れていない環境”に弱いタイプは、声が出なくて当然
もう一つの原因は、「慣れていない場面で声を出すこと」に対する脳と体の反応です。
普段から雑談や会話が少ない人は、そもそも“他人に聞かれる前提で話す”という経験が少ないです。
そのため、いざ緊張感の高い場で声を出そうとすると、喉や口周りがスムーズに動かず、震えや詰まりが起こりやすくなります。
これは決して特殊なことではなく、準備と慣れで改善できる“反応”のひとつです。
つまり、コミュ障で声が震えるのは「仕方ないこと」であり、責めるのではなく「慣れる」方向で対策すれば、ちゃんと話せるようになります。
コミュ障就活生がよくやる声の震え・どもりを悪化させるNG対策
面接前に「頑張って話さなきゃ」「声を張らなきゃ」と気合いを入れすぎて、逆に声がうまく出なかったこと、ありませんか?
私もかつて、面接直前に「よし、今日は大きな声で堂々と!」と自分を鼓舞し、結果として普段と違う話し方になってしまい、空回りした経験があります。
ここでは、コミュ障タイプの就活生がやりがちな、“逆効果になる対策”を3つ紹介します。
頭の中だけで練習して“口が追いつかない”
想定質問への答えを頭で考えることは大事ですが、口に出さずに準備していると、いざ本番で言葉が滑らかに出てきません。
私も初期の頃は、ノートにびっしり答えを書いて安心していました。
しかし、実際に話すと途中で詰まり、「こんなはずじゃ…」と焦ってしまいました。
頭の中と声に出す練習は、まったく別のスキルです。
「うまく話そう」と意気込みすぎて余計に固まる
「ちゃんと伝えなきゃ」「完璧に答えなきゃ」と意識しすぎると、逆に頭が真っ白になって言葉が出なくなることがあります。
特に真面目で一生懸命な人ほど、“正しく話す”ことにとらわれてしまいやすいです。
私も何度も、「この質問はこう返すべき」と頭で組み立てた結果、本番ではそれがプレッシャーになり、うまく言えなかったことがありました。
声を張ろうとして不自然になり、ますます焦る
「声が小さいから大きくしよう」と頑張りすぎると、普段と違う声の出し方になり、息が詰まって余計に不安定になります。
面接官の立場から見ても、無理に声を張ろうとして不自然になっている学生は、かえって緊張感が伝わってしまうものです。
大事なのは「大きな声」ではなく、「安定した声」。
そのためには、次に紹介するような“日々の練習習慣”が効果的です。
コミュ障でも声が安定する“ミニ声トレ習慣”【毎日3分】
「本番で声が震えるなら、普段から出し慣れておけばいい」
それに気づいてから、私は“話すこと”を特別なことにしない練習を少しずつ始めました。
ここでは、面接で声が震えやすい人でも続けやすい、1日3分の声トレ習慣をご紹介します。
ステップ①:声を出すこと自体に慣れる(1人ごとからでOK)
いきなり面接練習をするのではなく、まずは日常的に声を出す時間を増やすことが最初のステップです。
- 朝起きたときに「おはよう、自分」と言ってみる
- 家でパソコン作業中に「あ、これで合ってるな」など、つぶやく
- 天気や予定を「今日は晴れ。13時からバイト」など声に出す
私もこの「独り言習慣」を始めてから、声を出すことへの抵抗がグッと減りました。
ステップ②:「あいうえお」だけでも毎日動かす
滑舌や発声に自信がない人は、口の筋肉が固まっていることが多いです。
簡単にできるのが、「あいうえお」をはっきりと10回ずつ声に出す練習。
ポイントは、“大きな声”より“口の動きをしっかり意識する”こと。
慣れてきたら、文章にして「アイウエオ体操」のように言うのもおすすめです。
ステップ③:面接用のフレーズだけ音読で練習する
本番を意識した練習は、「全部通しでやろう」とせず、最初の一言だけを繰り返すのが効果的です。
たとえば、
- 私の強みは○○です
- 御社を志望する理由は○○です
- 大学時代、最も力を入れたのは○○です
この“言い慣れたフレーズ”があると、本番でも安心感が違います。
私も、「最初の一言だけ音読する」練習を続けたことで、声がぶれにくくなりました。
重要なのは、「話し慣れている状態」をつくること。
毎日3分の声トレでも、十分に“震えにくい声”を育てられます。
関連記事
「声が小さい」「滑舌が悪い」と不安な方は、声を届けるコツをまとめたこちらの記事もチェックしてみてください。
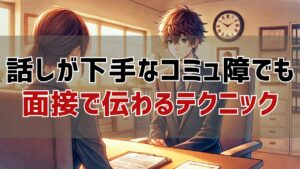
面接直前にもできるコミュ障就活生のための声の安定ルーティン
「準備はしてきたけど、面接直前になるとやっぱり声が震える」
そんなときこそ頼りになるのが、面接前の“声を落ち着けるルーティン”です。
これは私自身、面接前にトイレの個室などで毎回やっていた“お守り代わり”の習慣でもあります。
深呼吸→口を開くストレッチ→一拍置くクセをつける
まず、呼吸が浅くなっていることに気づくところからスタートです。
- 深くゆっくり息を吸って、長く吐く(×3回)
- 口を「うー」「ぱっ」と大きく開閉して緊張をほぐす
- 面接室に入る前に、一度立ち止まって「一拍置く」
この“間”を入れるだけで、声の震えがかなり和らぎます。
私もこの3ステップを毎回やるようになってから、「第一声が安定して出せる」感覚をつかめるようになりました。
「話し出す第一声だけ意識する」と安定しやすい
面接全体でうまく話そうとするとプレッシャーがかかります。
でも、“第一声だけ丁寧に出せればいい”と決めておくと、気持ちがグッと軽くなります。
たとえば面接の入り口で、
- 「よろしくお願いいたします」
- 「○○大学から参りました、□□と申します」
この最初の声が落ち着いて出せれば、その後も比較的スムーズに進みやすくなります。
私が面接官として学生を迎えたときも、第一声が丁寧な人は、それだけで“きちんとした印象”を与えられていました。
つまり、全部を完璧にする必要はなく、“最初の声の出し方”だけ意識すれば、全体の印象も自然と整っていくのです。
関連記事
もし、「緊張で頭が真っ白になる」「沈黙が怖い」と感じる方は、事前の心構えや回避法をまとめたこちらも役立ちます。

コミュ障が取り入れたい“話し方の安心型テンプレ”
声が震える、どもる、言葉がうまく出てこない。
このような経験が多くなると、そんな自分に対して「また失敗するんじゃないか」と不安になるのは当然です。
でも、私自身が就活の中で気づいたのは、“話し方に逃げ道を用意しておく”だけで、気持ちがだいぶラクになるということでした。
ここでは、緊張しやすい人でも安心して使える“話し方テンプレ”を2つご紹介します。
「すみません、少し緊張していて…」と最初に言ってしまう
緊張が表に出てしまいそうなときは、先に“緊張していること”を言葉にしてしまうのが効果的です。
たとえば、
「すみません、少し緊張していて、お聞き苦しいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。」
と言うだけ自分のハードルが少し下がります。
面接官側も「誠実な学生だな」「ちゃんと準備してきたんだな」と好印象を持ってくれることが多いです。
実際、私が面接官の立場だったときも、この一言を素直に言える学生は、むしろ信頼感が高まるケースが多かったです。
「〜と考えています」と締めるだけで話に“芯”が生まれる
どんなに話の途中が詰まっても、最後の一文がしっかりしていれば印象はグッと引き締まります。
たとえば、
なので、私はチームの中で調整役を意識してきました、と考えています。
これまでの経験から、相手の立場を想像する力を大切にしている、と感じています。
この“言い切るフレーズ”があると、多少途中が崩れても、「軸がある話」として評価されやすくなります。
これは私自身が、面接で話が途中であやふやになっても、最後の一言を丁寧に締めたことで「ちゃんと考えてるね」と言われた経験から得た実感でもあります。
不安なときほど、「始まりと終わり」だけ整えておくことが、安心して話すための支えになります。
声が震えるコミュ障でも誠実さで印象を残す話し方
コミュ障だった私からすると、“話せる人が評価される世界”が就活だとずっと信じていました。
しかし、面接官としてたくさんの学生と向き合ってきて180度変わりました。
就活では、話す内容や話し方よりも、“どう伝えようとしているか”の姿勢こそが、最も印象に残るということです。
無理に明るくする必要はない/“丁寧な音”のほうが信頼される
声が大きくなくても、滑舌がよくなくても、
- 語尾まで言い切る
- 相手を見て話そうとする
- 一言一言をゆっくり届ける
このような「丁寧な音」には、人柄がにじみます。
明るく元気に話せるタイプではなかった私でも、「すごく落ち着いていて、信頼できそう」と言われたことがありました。
それは、話し方そのものより、“丁寧に話そうとする姿勢”が伝わった結果だったのだと思います。
面接官は「完璧な滑舌」より「思いがこもっているか」を見ている
私自身、採用担当として学生の面接を見てきたときの印象をお話します。
スラスラ話せるけど心がこもっていない人より、緊張して言葉に詰まりながらも、“一生懸命伝えようとしている人”のほうが印象に残りました。
面接官が見ているのは、滑舌の良さやテンションではなく、「この人と一緒に働けるか」「信頼できそうか」という人柄の部分です。
つまり、声が震えても、どもっても、“あなたの姿勢や誠実さ”がきちんと伝われば、それだけで合格圏に届くということです。
まとめ:「声が出ない」は性格じゃない。コミュ障こそ“話せる準備”で巻き返せる
面接で声が震えると、「自分はコミュ障だからダメなんだ」と思ってしまいがちです。
ですが、一概にそうとは言えません。
というのも、声が出ないのは“性格”ではなく、“準備の不足”でしかないからです。
そして、準備さえできれば、コミュ障でもちゃんと伝わる声は出せるのです。
この記事で紹介してきたように、
- 日々の声トレで「話し慣れた状態」をつくる
- 面接直前のルーティンで緊張を和らげる
- 最初の一言だけを決めておく
- 緊張を正直に伝える安心フレーズを用意する
- 誠実さがにじむ“丁寧な話し方”を意識する
この5つの工夫を組み合わせることで、声が震えていた私でも、面接で「落ち着いているね」と言ってもらえるようになりました。
話すのが得意じゃなくてもいい。震えても、どもっても、“話そうとする姿勢”があれば、ちゃんと伝わる。
コミュ障こそ、“自分らしい伝え方”を準備することで、面接の場を乗り越えられます。
「どうしても本番が怖い」という方は、面接本番に強くなるための練習ステップをまとめたこちらの記事もご覧ください。