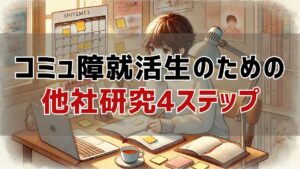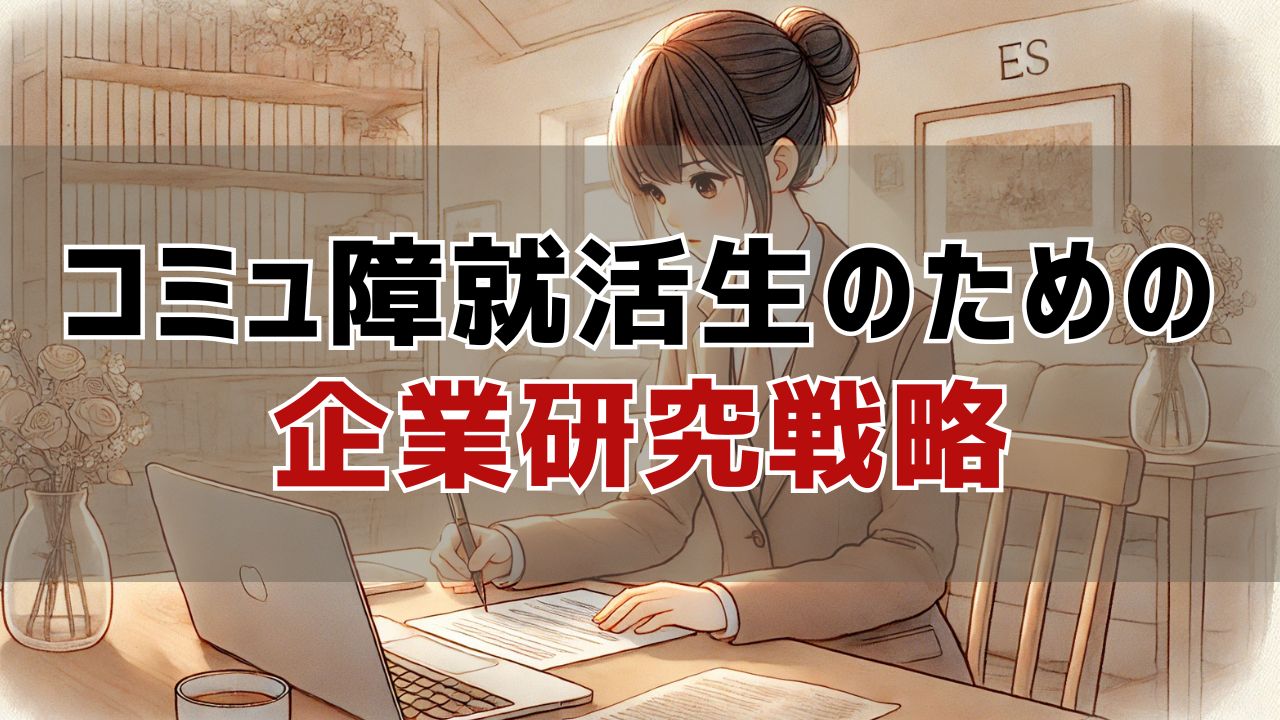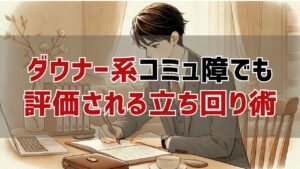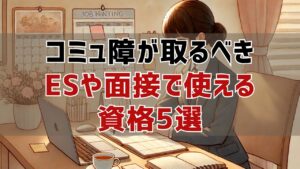「企業研究」と聞くと、情報を集めて比較して…という作業を想像して、正直うんざりしてしまう人もいるかもしれません。
特に、コミュ障気味で話すことに不安を抱えている就活生にとって、
- どんな会社が自分に合うのか
- どこなら無理なく働けるのか
を見つけるのは、自己分析以上に重たく感じる作業かもしれません。
でも、私自身がそうだったように、企業研究をしていたからこそ、“話せなくても戦える準備”ができたと今では思っています。
そこで、この記事では、
- 企業研究が苦手なコミュ障就活生こそ、企業研究をやるべき理由
- 面接で話しやすくなる企業研究のやり方
- 声が小さい・会話が苦手でもできる企業研究の3ステップ
- 比較より「違和感のなさ」で企業を選ぶ方法
- 志望動機・逆質問を自然に用意できるようになる考え方
を元コミュ障就活生、そしてその後採用担当としても多くの学生を見てきた立場から解説していきます。
「話せる人向け」の就活対策にモヤモヤしていた人にこそ読んでほしい内容です。
コミュ障就活生の企業研究をやることの3つのメリット
私の就活初期は「企業研究って必要なの?」と思っていました。
特にコミュ障気味だと、集団説明会の情報やパンフレットを見てもピンと来ないし、調べても何を見ればいいかわか李ませんでした。
でも実は、話すのが苦手な就活生ほど企業研究の“深さ”が武器になるんです。
ここでは、その理由を3つのメリットとして紹介します。
話すことが苦手でも面接で話す内容が見つかる
面接が苦手な人の多くが悩むのが、「何を話せばいいのかわからない」ということです。
でも、企業研究をしておくと、その会社ならではの特徴や、自分との共通点が自然と見つかります。
たとえば私は、ある企業の社員紹介ページを読んで「現場の声を大切にする風土がある」と知りました。
この内容を見たことで、「私も現場の意見を吸い上げる姿勢を大事にしてきた」という経験を自己PRに盛り込むことができました。
つまり、自分のエピソードと企業の考え方をつなげることで、話す内容に“意味”が出てくるんです。
元面接官としての視点から言えば、話す内容の完成度よりも、「その会社に興味を持ってくれているか」「自分の言葉で語っているか」を重視して見ていました。
たとえ話し方がたどたどしくても、企業研究に基づいた一言には説得力があります。
合わない企業を早めに除外して無駄なエネルギーやストレスを減らせる
就活中、すべての企業に同じようなモチベーションで向き合うのは無理です。特に、話すことに不安がある人にとって、1回1回の面接は大きな消耗になります。
だからこそ、合わなそうな会社は早めに「除外」することが自分を守る戦略になるんです。
私の場合、体育会系の雰囲気が強い企業を調べて「無理だな」と思ったら、応募すらしませんでした。
そこで無理にチャレンジしていたら、面接で沈黙した自分をまた責めていたと思います。
「企業研究=受ける企業を見つける作業」と思いがちですが、実は「受けない企業を決める作業」でもあるんです。
志望動機や逆質問が自然に準備できて緊張対策になる
面接が怖いのは、「何を聞かれるかわからない」「何を答えればいいかわからない」からです。
でも、企業研究を通して相手のことを知っておくと、志望動機も逆質問も“準備できる話題”になります。
たとえば、企業の強みや新しい取り組みに注目しておけば、
- 志望動機
○○という取り組みに共感して応募しました。 - 逆質問
この取り組みに関わる機会は若手にもあるのでしょうか?
と、相手の土俵で会話を組み立てることができ、必要以上に緊張しにくくなります。
私も、「自分のことを聞かれるのが怖い」と感じていたタイプですが、企業の話題から入ると、落ち着いて会話できた経験が何度もあります。
企業研究を志望動機にどう落とし込めばいいかわからない方は、志望動機の書き方を解説したこちらの記事もおすすめです。
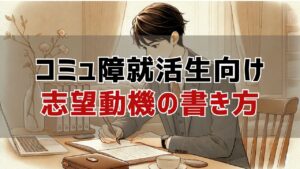
コミュ障の企業研究は広く浅くより1社ずつ深くがポイント
就活サイトでは「できるだけ多くの企業を見るべき」とよく言われますが、これは情報処理が得意で、社交的に立ち回れる人向けのアドバイスです。
コミュ障気味の就活生にとっては、企業ごとの微妙な違いを大量に比較するよりも、「ここなら安心して働けそう」と思える1社を深掘りするほうが、ずっと効率的で実用的です。
私も就活初期は「○社比較」とか「業界全体を知ることが大事」といった情報に惑わされて、混乱していました。
でも、結局エントリーしたのは「違和感がなかった」会社だけです。
そこに注力したほうが、準備も自然に進みました。
比較より「違和感のなさ」で選ぶと迷いが減る
「なんとなく気になる」
「なぜか安心する」
そういった感覚は、就活においては立派な判断材料です。
人と話すのが苦手な人ほど、職場の雰囲気や空気感に強く影響を受けるものです。
だからこそ、「違和感を感じない会社」を探すのは、戦略的な選び方だと言えます。
実際、私はある企業の説明動画を見たときに、「この人たちと話すのはなんか怖くない」と思ったことをきっかけにエントリーを決めました。
結果的にその企業の面接では落ち着いて話すことができ、内定もいただけました。
反対に、かっこいい社風や待遇面に惹かれて応募した企業は、どこかで自分を無理に作ってしまい、うまくいかなかった経験があります。
情報量より「納得感」を優先してOK
企業研究で陥りがちなのが、
「もっと調べなきゃ」
「情報が足りないかも」
という不安です。
特に真面目なタイプの人ほど、完璧な準備を求めて疲弊してしまいます。
でも、就活の本質は「自分が納得して働ける場所を選ぶこと」。
情報の多さより、自分の感覚に合っているかどうかのほうが大事です。
たとえば私は、5社くらいを深く調べただけで「自分に合う会社の基準」が見えてきて、それ以降の選考も無駄がなくなりました。
情報を集めすぎて動けなくなるより、「自分なりに納得できたら、それでOK」と決めることが、行動につながるコツだと思います。
コミュ障でもできる!負担の少ない企業研究3ステップ
企業研究というと、「会社四季報を読み込む」「IR資料を見る」など、いかにも真面目で情報量が多そうな方法を想像しがちです。
でも、それではハードルが高すぎますよね。
特に、話すことが苦手だったり、情報を整理するのが得意ではない人にとっては、調べること自体がストレスになります。
そこでおすすめなのが、“空気感”や“感情”を基準にする企業研究のやり方です。
これは私自身が試行錯誤しながらたどり着いた方法で、今でも「もっと早く知りたかった」と思っています。
以下の3ステップは、できるだけ負担を減らしつつ、話すための準備にもつながる方法です。
ステップ① 社員紹介・社風動画で“言葉より空気感”を見る
会社のホームページにある「社員インタビュー」や「会社紹介動画」は、文字情報よりも雰囲気が伝わりやすい素材です。
ここで注目してほしいのは、言っている内容よりも“その人たちの話し方や雰囲気”です。
たとえば私は、ある企業の動画を見て、「あ、この人のしゃべり方、私と似てる」と思えたことで、「ここなら自然体で話せそう」と感じました。
実際に面接を受けたときも、必要以上に自分を作らずに済みました。
言葉が苦手な人こそ、“言葉じゃない部分”から感じ取れる情報を大事にしてほしいと思います。
ステップ② 口コミ・SNSで“自分の感情に合う会社”を探す
就活会議やOpenWork、X(旧Twitter)などには、社員や就活生のリアルな声が転がっています。
もちろんすべてを鵜呑みにする必要はありません
ですが、「この会社、なんか苦手かも」「この投稿者の感じ方、共感できる」といった感覚は、かなり参考になります。
私も、ある企業の口コミで「声が大きい人が多く、会議は活発」という内容を見て、「ちょっとしんどそう…」と感じて候補から外したことがあります。
コミュ障の人にとっては、自分の感情に引っかかる情報を信じることが、ストレスを避けるコツになります。
ステップ③ 志望動機テンプレに企業情報を当てはめて整理する
企業研究のゴールは「自分の志望動機にどうつなげるか」です。そこで使えるのが、テンプレートを活用した書き出しです。
たとえば、こんな形で整理してみてください。
- 貴社の◯◯という点に惹かれました
- 私はこれまで◯◯な経験をしてきました
- その経験と貴社の◯◯が重なると感じ、志望しています
このテンプレに、さきほど得た社風の雰囲気や自分の感情を当てはめることで、オリジナルの志望動機が無理なく作れます。
話すのが苦手でも、「内容が決まっていれば緊張が減る」という人には特におすすめです。
ただ、「企業研究はしたのに、話が浅くなる気がする…」と感じる方も中にはいらっしゃると思います。
そのような人は“中身のある話”に変えるための構成法をまとめたこちらの記事も参考になります。
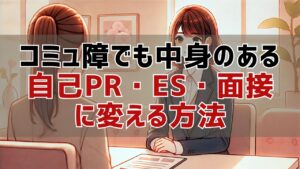
コミュ障就活生が企業研究ノートに書くべきこと
企業研究をしても「調べただけで終わってしまう」「何を記録すればいいかわからない」という声もよく聞きます。
私自身、最初はメモ帳に公式サイトの文章を写して終わっていました。でもそれでは、面接でまったく活かせませんでした。
そこでおすすめなのが、「調べた情報」ではなく「自分が感じたこと・使えること」をノートに書いておくことです
ここでは、実際に私が企業研究ノートに書いて役立ったポイントを3つご紹介します。
ポイント①「合いそう・合わなそう」を“自分の言葉”でメモする
企業研究で最も大事なのは、「自分がどう感じたか」を言語化しておくことです。
たとえば、「この会社は丁寧に話す人が多くて安心した」とか、「元気すぎて圧倒された」など、“事実”ではなく“印象”を書くことがポイントです。
私のノートには、「ここは話しかけられたら返せそう」「ここは黙ってると浮きそう」といったメモが並んでいました。
こうした感覚的な記録こそが、企業選びの軸になります。
ポイント②「この会社なら話せそう」と思った根拠を記録しておく
面接で緊張する人にとって、「この会社なら話せそう」と思える理由を先に見つけておくことは、かなりの安心材料になります。
たとえば、
「社員紹介にあった“緊張しやすい人が多い”という言葉に救われた」
「オンライン説明会の雰囲気が穏やかだった」
など、自分にとって安心できる“根拠”を残しておくのです。
面接前にそのメモを見返すだけで、「大丈夫、ここなら大丈夫」と気持ちを整えられます。
ポイント③ 比較より“違和感のなさ”で企業を分類する
Excelやノートで企業を比較しようとすると、「待遇は?」「福利厚生は?」と項目が増えて、逆に疲れてしまうことがあります。
そこでおすすめなのが、“違和感がないかどうか”を基準にゆるく分類するやり方です。
たとえば、
- A社:空気感がちょうどいい
- B社:テンション高めで自分には合わない
- C社:話す相手を選べばなんとかいけそう
のように、「どのくらい自然体でいられそうか」で企業を分けていくと、志望度の優先順位もつけやすくなります。
まとめ|企業研究は情報収集より「安心できる会社探し」として使おう
企業研究というと、「調べること」や「他人より詳しくなること」が目的だと思われがちです。
でも、コミュ障就活生にとっての企業研究は、情報収集ではなく“安心できる会社”を探すためのプロセスとして使ったほうが、圧倒的に意味があります。
就活をしていると、「もっと情報を集めなきゃ」「志望動機を完璧にしなきゃ」と焦る場面も多いです。
ですが、私の経験から言えるのは、“自分が安心できる会社”に出会えたときほど、自然に言葉が出てくるということです。
自分が話しやすそうだと思える会社、違和感を覚えなかった会社、何となく合いそうと思った会社。
そうした感覚を大事にして企業研究を続けていけば、無理に変わらなくても、“やり方”を変えることで十分に戦えるようになります。
企業研究を続けていく中で、「他社とどう比較すればいいの?」「比較するほど迷ってしまう…」という方もいます。
そのような方は、比較NGパターンを避けるための他社研究戦略も参考になりますので、以下の記事も参考にしてください。